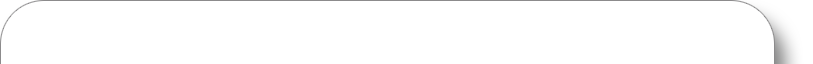今年の秋は、快晴が続き20-25℃で最高です。夏が寒かったので、その埋め合わせでしょう。この数日は、6月に倒れたポプラの樹(20m)の枯れ枝を燃やす作業で汗をかきました。
私たちが率先して真実を選ぶ。その姿勢を保つ何か良いヒントはありますでしょうか。
お役にたつかどうか自信はありませんが、体験的に語ってみたいと思います。(フランスで暮らしながら、哲学的に語れないのは残念です!?)三つのテーマ、従軍慰安婦、特攻隊、昭和天皇実録に関するものです。
高橋源一郎さんの朝日の論壇時評コラム,ぼくも愛読しています。「戦争と慰安婦」(8月)で高橋さんは、慰安婦に関する2冊の小説、田村泰二郎の『蝗』と古山高麗雄の『セミの追憶』を紹介し、代表的文献といわれる秦郁彦氏の『慰安婦と戦争の性』で、「慰安婦の証言は信じるに足りない」との彼の発言への違和感を語っています。‘これで切り捨てるのは冷たい’同感です。
もう20年前になるでしょうか。有楽町の外国特派員クラブの図書館での光景です。韓国人ビジネスマンの会員(60歳?)が、日本の新聞の「慰安婦について軍の関与はなかった」との見出しを見ながら、大きな声で「いい加減にしてくれよ」と独り言を発しました。‘なぜ、こんな屁理屈を言っているのだ’とぼくには聞こえました。
高橋さんが挙げた上記の2冊の小説、秦氏の著作、それにインターネットで見つけた小説“Comfort Woman”Nora Okja Keller”(韓国系米国人女性作家、NYT書評が称賛)を読み勉強したいと思っています。
保坂正康さんの毎日新聞のインタビュー「特攻隊は日本の恥部、美化は怖い」をご覧になったと思いますが、勇気ある発言だと思います。高校生のとき『きけわだつみのこえ』を読んで以来、軍への怒りを梃に昭和史の権威となった彼が「特攻隊のおかげで今の日本がある」など軽々しく言うな、との指摘同感です。
今年、亡くなった友人の米国人記者サム・ジェームソン(ロスアンゼルス・タイムズ紙などの東京支局長、在日50年)が、歴代の首相は8月15日に「戦争で亡くなられた方々の犠牲のうえに、今の日本があると言うが、正確には‘犠牲にもかかわらず’ではないのか」と語っていました。ハットしたのを覚えています。わたしが知る限りこの辛い真実を公言したのは、保坂さんがはじめてです。
映画『永遠のゼロ』を見た同年代の友人が「すがすがしい映画だった」と言いました。
ぼくは「特攻隊については、なぜこんな悲劇が起こったのか、を語るべきだ」と言いました。『きけわだつみのこえ』を再読し、以前に英国エコノミスト誌の書評が高く評価していた“Kamikaze Diaries”Emiko Ohnuki-Tierryを読書リストに入れます。
『昭和天皇実録』への評価は、「文芸春秋」10月号の特集と毎日新聞のインターネット版で読んだくらいですから、あまり日本の識者の反応は知りません。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙の二つのコラムは、おそらく日本では報道されていないと思うので、ご紹介しましょう。
米国人のハーバート・ビックス教授が同紙(9月29日)に寄稿したコラムに次のような記述があります。「日本の大新聞から『昭和天皇実録』についてなにか書いてもらえないか、と依頼があった。ただし、天皇の戦争責任以外のことなら、なんでもいいので、と担当者は言った。わたしはこれを断った」。ビックスは天皇の戦争責任をテーマにした『昭和天皇』(講談社学術文庫)を書きピュリッツアー賞を受賞した歴史家ですから、この原稿依頼は滑稽そのものです。その新聞社はどこかわかりませんが、天下に恥を曝したことになりますね。
加藤典洋さん(文芸評論家)の同紙への寄稿(10月14日)は、おそらく僕らの世代の多くの日本人の思いを代弁しているコラムだと思います。彼は、ビックスの体験に触れ、これは日本では天皇の戦争責任がいまだにタブーであることを示していると指摘し、1975年10月31日の皇居での昭和天皇記者会見のことを語ります。
その席での中村浩二記者(ロンドンタイムズ)の質問。「天皇陛下はホワイトハウスで“私が深く悲しみとする不幸な戦争」という発言をされましたが、このことは戦争に対して責任を感じておられるという意味と解してよろしゅうございますか。また、陛下はいわゆる戦争責任についてどのようにお考えなっておられますかお伺いします」。その問いへの昭和天皇の答えは「そういう言葉のあやについては,私はそういう文学方面はあまり研究していないのでよくわかりません。そういう問題についてはお答えが出来かねます」という禅問答みたいなものでした。。
加藤さんは、この記者会見に参加していた唯一の外国人マイク・ソープ記者(ぼくの友人)が翌日のデイリー・マイニチ紙で、その場の雰囲気を伝える記事を引用しています。「タブーを破ったその質問に会見場は一瞬凍てついた。しかし、すぐ誰もが尋ねたかった質問だったので、ほっとした空気になった。中村記者の質問は前代未聞の質問で、戦後唯一のものである、と加藤さんは感慨を込めて書いています。ぼくは中村記者のジャーナリスト魂に敬意を表します。
ぼくは真珠湾攻撃の年に生まれたから、なぜあのような愚かで無謀な戦争をしたのかについて関心があり、いろいろ読んできました。そのなかに、原書房が刊行した『杉山元日記』があります(杉山は参謀総長(1940-44年)で、終戦の年、割腹自殺をした将軍)。手元に本がないので正確な引用はできませんが、1941年1月、彼は天皇に真珠湾攻撃計画を報告し、それを聞いた天皇はその計画の研究を進めるよう指示と書いてあった記憶があります。実際の攻撃11か月前のことですが、その後も計画の進捗を参謀長は大元帥陛下に報告していたと思ってもおかしくありません。『昭和天皇実録』でこのことをどう扱っているか、興味があります。
冒頭に挙げた3つのテーマは、戦争にからむことで相手があります。ですから、韓国、北朝鮮、米国などの連合国の人びとがどう考え、どのようにその体験と事実を記録しているか、を理解する必要ありです。ぼくはそのことを心がけています。たとえそれが苦くても、歴史の真実を怖れることはない、と思います。
土野繁樹
(27) 2014.11.05
「公開対話26」を一読、ぐっと臓腑をえぐられるような読後感がありました。重いのですが、同時に誤解を恐れずにいえば、さわやかでした。保坂正康さんのエッセー(「特攻隊は日本の恥部、美化は怖い」)と土野さんのエッセーは木魂するように、ひとつのテーマが広がる感じがしました。
私が学生だった1970年代は、「昭和天皇の戦争責任」を問う声はありました。高校時代の友人には、いわゆる「左翼」も「右翼」もいたので、両翼からの眺めが少しばかり見えていた気がします。どちらもそれなりの理論や理念があり、歴史を見る角度があり認識があることは理解できました。いささか極端だと感じ、どちらにも与(くみ)することはできませんでしたが、真摯に「真実」を求め、主張する姿は潔いものがあるとは感じていました。
しかし1980年代に入ると、「昭和天皇の戦争責任」について論議する人は少なくなったように記憶します。自分が社会人になり、仕事の忙殺されるようになっただけで、世の中の論争は続いていたのかもしれませんが。偶然か必然化はわかりませんが、入れ替わって1980年代に次第に広がっていったのが「従軍慰安婦問題」でした。
「特攻」について、保坂さんが記したことを読むと、私たちにとって「戦争」は未だ終わらないテーマなのだと、あらためて実感させられます。「特攻」は突出した事象でしたが、「玉砕」もまた、劣勢になった日本軍が繰り返しました。保坂さんは、「特攻は日本の恥部です。命を慈しむ日本の文化や伝統に反することです」と主張しています。私も本来の日本人は、命を慈しむ文化や伝統をたいせつにしてきたと思います。しかし、こと戦争となったとき、それが脆くも崩れたのはなぜか。「歴史的事実」の奥にある「歴史の真実」が問われている気がします。
よく引き合いに出される例ですが、「女王が亡くなり、その後まもなく、国王が亡くなった」は「事実」の記述。これに対し、「女王が亡くなり、その悲しみのあまり、国王も亡くなった」が「真実」の描写。客観的「事実」にこだわれば、国王の死因は、「悲しみ」ではなく、心臓の疾患など、なんらかの医学的理由で説明されるべきなのですが、それではわからないことがある。かといって、「悲しみ」と死を結びつける因果関係は証明がむつかしく、一種の主観的ストーリーに過ぎないのではないか。事実に謙虚であり、その上で、その奥にあるものを見る。単なる主観を超える視点がきっとあるのだと思います。
「真実を選ぶ」ことについて、土野さんが体験的事例をもって示唆されたこと。それは、簡単には答えが出ない重い問いを、重いまま担ぎ続け、問い続けるメンタルスタミナを持て、ということだと受け止めました。重いのに、さわやかな理由は、きっと問い続ければ真実がいつかわかるという希望を感じさせてくれたからだと思います。土野さんから提示いただいた3つのテーマ「昭和天皇の戦争責任」「従軍慰安婦」「特攻」は、日本人にとって、容易に答え(正解)の出ない問いを、とにかく問い続けるべき課題なのかもしれません。
「歴史的事実」を正しく知る、という意味では、今回の土野さんのエッセー「
パリは燃えているか?」もまた白眉でした。
ノルマンディー上陸作戦のガルボにつづき、驚きの歴史秘話となりました。 「パリは燃えているか?」は、映画のタイトルとしては知っていたのですが、このような内容でしたか・・・。戦争の時代における外交の力を知りました。勇気づけられる話です。
「歴史の証言台に立つ覚悟」
未来の一点から現在の自分を見つめる視点がいかに大事か、痛感しました。フォン・コルティッツの苦悩は、決して歴史話に終わらない、市井の人々にも役立つ教訓があります。日本の軍人や政治家、外交官でこういう逸話をもつ人はいるのでしょうか。ナチスの迫害を受けたユダヤ人を救済した外交官の杉原 千畝はそうした尊い事例ですね。
『外交官』の監督シュレンドルフは「バリが焦土になっていたら、戦後の仏独和解は極めて難しかっただろう」と語っている。
一気に読ませて、このエンディング。現在の自分たち(人類)のあり方に直結するのが歴史だと実感できました。こうして私たちは、エッセー(5)「
仏独和解50周年」に再び導かれます。土野さんのエッセーは、重層的に読み込む価値があります。『外交官』の監督の言葉は「歴史的事実」を語ったわけではありません。しかし、土野さんのエッセーを読了したあとでは、「歴史の真実」の一面にくっきりとスポットライトを当てたものと実感できました。
「正確に事実だけを伝えながら、これだけ心に入って行く文章って、本当にすごい。」
エッセー「パリは燃えているか?」を読んだ私の元同僚の女性の感想です。
梅本龍夫
(28) 2014.11.23

先日は日比谷の春秋ツギハギでご馳走になりながらの、河村さんを交えての鼎談は愉快でした。7ヶ月ぶりの帰国ですが、高倉健の死、衆議院解散と突然のニュースにおどろいています。
若いころ、健さんに麻布にあった「クラークハッチ」スポーツ・クラブの狭いサウナで会ったことがあります。「高倉さんは北九州のご出身ですが、わたしは下関です・・・」と自己紹介をして、数分会話を交わしました。会話の内容は覚えていませんが、礼儀正しいさわやかな人との印象が残っています。40歳の健さんは筋肉質のいい体をしていました。 彼の最後の作品『あなたへ』は門司も舞台ですが、関門海峡を見ながら育ったぼくにとって心に残る作品です。
マイケル・ダグラスと彼が演じた二人の刑事のストーリー『BLACK RAIN』をご覧になったことありますか。この作品で、健さんは国際スターになりましたが、”日米刑事道“のちがいなども描いた実に面白いアクション映画でした。
海外では、彼は日本のクリントン・イーストウッドと言われているようですが、これは当たってませんね。彼が尊敬した俳優フランスのジャン・ギャバンの日本版ではないでしょうか。とくに晩年の味のある役がそうですね。ただし、洒落た女性関係は健さんの映画にはでてきませんが。
彼は「5分でも10分(これは眉唾ですが)でも黙ったままだった」とその寡黙な人柄を偲んだ知人の談話がいくつかありましたが、一方では、親しい友人は「よく笑い、しゃべり、ユーモアのセンスがあった」と言ってますから、どちらも本当なのでしょうね。ユーモアのセンスは、ぼくの人物評価の重要ポイントですから、これを知り嬉しくなりました。
あるファンが彼を追悼して「日本の男としてのあるべき姿を学んだ」と言っていますが、これいいですね。
毎日新聞が彼の死と解散を伝えた日の一面に、健さんと安部首相の写真が並んでいました。高倉健は中国で大人気の俳優で、『君よ憤怒の河を渉れ』は1億人が見たといわれています。日中共同制作の作品にもでていて、あの人柄ですから中国人の信頼もあるのでしょう。
‘健さんが日本国の首相だったら、日中関係は’友好第一、勝負は第二‘(周恩来の外交)なのになあ’とため息をつきました。
梅本さん、友人の方の感想、書き手冥利につきます。ありがとうございます。このエッセーを書きながら、歴史は人がつくるものとの感を強くしました。どんな人生でも、重大な岐路に立つことがありますが、そのとき誰がなんと言おうと自分で決める覚悟がいると思います。昭和天皇は大元帥として、対米戦争を回避する権限があったが、それをやらなかった。その意味で、天皇の戦争責任は重いと思います。
今日、本の整理をしていて山本七平の『一下級将校が見た帝国陸軍』(文春文庫)を見つけました。学徒動員で徴兵されフィリッピン戦線に送られ米軍と戦い捕虜となった体験をつづった作品ですが、ぼくは戦争体験者が書いたノンフィクションの最高作品だと思っています。そのなかに、捕虜収容所のなかでの一場面―将軍たちはなにもなかったかのように「閣下」と呼び合い和気藹々と碁を打っていた。「あのときは、ああするしかなかった」という雰囲気であった。この「あのときは・・・」というのが曲者ですね。
山本七平は『空気の研究』(文春文庫)で、日本では空気が世の中を支配すると言ってます。戦前は「米英なにするものぞ」という空気が醸成(醸成元は軍部、政治家、マスコミ)され、国民はそれを信じて、天皇がこの空気にのったという図式でしょう。日本は空気が支配するだけでなく、責任体制が明確でない社会ですから、将軍たちは戦争に負けたのはまるで自然現象のような態度で、和気藹々とやれたのではないでしょうか。
里帰りをして2週間、伊豆の山の上ではTVがない暮らしでラジオを聞き、車で10分のところにあるファミリーマートで、毎日新聞を買い読んでいます。ご覧になったと思いますが、昨日の「首相お膝元 明と暗」は出色のルポ(
「大義」の陰で:2014衆院選/2 首相お膝元、明と暗 アベノミクス恩恵、富裕層止まり 「創生」「景気回復」地方に届かず - 毎日新聞)でした。選挙区である下関と居住地である東京富ヶ谷のアベノミクス効果の比較をして「残酷なまでのコントラス」を描いている記事で、今日の6ページもあるアベノミクス選挙記事より鮮やかに現状を描いていると思いました。大学の同級生で、下関の繁華街の4代目呉服店主である藤城君が「この店もいずれ消えてなくなるのかな」という言葉が身にしみます。それにしても、日本の新聞にはユーモアがありませんね。4コマ漫画に押し込むのはもったいない!
土野繁樹
(29)2014.12.10

先日は久しぶりにお会いし、いつにも増して楽しく充実した「まじめな雑談」のお時間をいただきました。ありがとうございました。ちょうど今月頭に事務所移転をし、ドタバタにかまけて「公開対話」の返信が遅れてしまいました。申し訳ありません。
数日前、土野さんの最新エッセー「パリは燃えているか?」
http://lgmi.jp/detail.php?id=2315を読んだ知人数人と会食をしたのですが、全員ここで語られた「歴史的事実」を知らず、一様に「事実は小説よりも奇なり、だね」と顔を見合わせていました。そして、上質なエッセーは、知識以上の何かをもたらすという意見でも一致しました。次回作も楽しみにしております。
高倉健につづき、菅原文太も亡くなりました。昭和の時代を象徴する男臭い俳優が相次いでこの世を去った今、平成の時代を象徴する男はどのような存在なのか、考えこみました。寡黙で、義理と人情に引き裂かれるタイプから、自己主張が強く、弁を弄し、経済的利益を最優先するタイプになっていくのでしょうか。それとも、男臭さを消した中性的(両性的)なやさしさや包容力をもつタイプになっていくのでしょうか。
『BLACK RAIN』は観ました。大阪の街のマンホールから湯気が立ち、とつぜんニューヨークのようになり、びっくりしました。SF映画の名作『ブレードランナー』のリアル・シティー版のような雰囲気に魅了されたのを覚えています。松田優作の遺作にもなり、記憶に残る映画です。
俳優は、時代の顔ですね。特に映画は、社会的な記憶装置にもなります。虚構の物語(フィクション)なのに、現実以上のリアリティーを実感させるからでしょうか。映像と音楽とセリフ、そして俳優の存在感によって、私たちは「拡張現実」を楽しむことができます。上質な小説やエッセーに通じる創作物の力。そういうものを、エンターテインメントだけでなく、社会的なテーマに応用する方法論を模索したいと思っています。
実は米国を中心とするマーケティングの先端的な考え方は、消費者に商品やサービスではなく、「ブランドの物語」を売り込む方向に発展しているといわれます。ジョナ・サックスというマーケターが書いた『ストーリー・ウォーズ』(英知出版)という本を最近読んだのですが、これが実に面白い内容でした。「物語」は私たちを動機づけたり、行動する勇気を与えてくれたりしますが、同時に巧妙にマインドコントロールをされるツールともなります。
この本の中で、著者のサックスは、伝説のコピーライター、ジョン・E・パワーズの逸話を紹介しています。パワーズは、「真実」にこだわりました。「虚偽」を広告することを潔しとしませんでした。そこで、あるべき広告の3原則を打ち出しました。第一が「刺激的であること(=広告は何よりおもしろくなければならない)」。第二に「真実を伝えること(=嘘や誇張を売り込んではならない)」。第三が「真実を実践すること(=伝えるべき真実がないなら、現状を見直して真実を生み出すこと)」。つまり、広告主のビジネスに誤りがあれば、それを正す必要があるということです。「ブランドの物語」の本質を突いている話だと思いました。
日本では衆院選の選挙運動真っ盛りです。自民党圧勝の流れがメディアで伝えられる中、人々は政治への熱量をもたず、投票率も低くなると予想されています。仕事関係の知人に聞いてみましたが、「選挙にはかならず行くようにしてきたが、今回はパスするかもしれない…」と言っていました。どうも、安倍政権・自民党の路線を追認する流れ、「空気」が醸成されているようです。それは、消極的なものかもしれませんが、アベノミクスの継続しか「道はない」とする、自民党のコピー文を受け入れるものになっていると感じます。
政治こそ、もっとも基本に「社会の物語」があるべきです。日本はどういう国家でありたいか、どういう社会を私たちは形成したいのか、私たちが向かう未来の理想はどのようなもので、どこに価値観の機軸を置くのか。ほんらい選挙は、そうした骨太な「国家の物語」を選択するたいせつな機会ですが、政治は巧妙に「真実」(ほんとうの物語)を回避し、語ろうとしません。代わりに、今の流れしかないな、という「空気」があたりを支配します。土野さんが指摘された山本七平の「空気の研究」にある典型的な日本の姿です。
本日(12/10)、特定秘密保護法が施行されました。リグミの解説で、そのことを「空気」として論じてみました。
http://lgmi.jp/detail.php?id=2372 拙い文章ですが、この法律がなぜ問題視されるのかを考える一助になればと思いました。日本社会特有の「空気」については、その功罪を一度しっかりと棚卸ししたいと思っています。山本七平は、「空気」に対抗する唯一の手段は「水を差す」ことと示唆しましたが、どうもそれだけではない気がします。ふわっとした「空気」に意味と構造を与え、自覚的に考えたり、見つめ直したりするきっかけを与えてくれる卓越した「物語」が一方に必要なのではないか。私の問題意識です。
フランスやヨーロッパ諸国には「空気」にあたるものはあるのでしょうか。政治や社会に一定の流れができたとき、それに「水を差す」のを控える雰囲気というのは、ありますか。スコットランドの独立運動(選挙)の終盤のプロセスなどにはそういうものも多少はあったのかもしれないと感じました。土野さんの観察やご意見など拝聴致したく思います。
梅本龍夫
アーカイブ