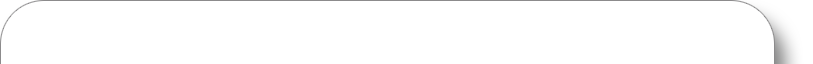(30)2015.01.07

明けましておめでとうございます。年末、伊豆の家の買い手が決まり、契約手続きと明け渡しでテンヤワンヤ、返信が遅くなり失礼しました。サン・ジャン村に戻ってきて2週間、豊かな自然に囲まれ江戸時代のペースで時間が流れるこちらが一番落ち着きます。
天皇の新年にあたっての所感「本年は終戦から70年という節目の年に当たります・・・・この機会に、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なことだと思っています」。これ安部内閣への強烈なメーセッジですね。(
天皇陛下、新年にあたっての感想全文:朝日新聞デジタル)
これを読み、明仁天皇ほど昭和の軍国主義の誤りを反省し、戦後の平和主義とデモクラシーを信奉する方はいないのではないか、との思いを深くしました。天皇の「日本国民は歴史に学ばなければならない」発言は、国際社会では通用しない「いびつな歴史観」を持つ首相と閣僚への警告とぼくはとりました。野党が弱体化している現在、天皇は日本の最大野党の役目を果たしていると思います。
フランスでは、昨年は第一次世界大戦開戦から100年、ノルマンディー上陸作戦、パリ解放から70年で、新聞、雑誌、TVは年間を通じて歴史に学ぶという観点で大きく扱っていました。日本のマスコミも戦後70年のこの機会に、大いに1945年の意味を報じてほしいと思っています。明治維新から73年で太平洋戦争へ突入し5年後に無条件降伏、第二の開国をして今年は70年ですから、数字の上では歴史のサイクルが似ています。
「歴史から学ばない者は同じ過ちを繰り返す」と哲学者サンタヤナが言いましたが、それを避けるためには、ファクトに基づいた戦争の記憶を次世代に伝えなくてはなりません。戦後、これが徹底していなかったために現在の歴史認識の混乱(戦後生まれの世代だけではなく、ぼくらの世代にも)があると思います。敗戦から70年のこの機会に、ジャーナリストと歴史家は満州事変以降の歴史を国民に正確に伝える義務があります。その際、忘れてならないのは、自国を客観視し対戦国、植民地の人びとの体験を正確に伝えることだと思います。
毎日と朝日はその意義を良く知り、戦後70年特集を始めていますね。朝日は満州事変(1931年)から日独伊三国同盟(1940年)までの歴史を簡潔に記述し、当時のニュース映画を添付しています。例えば、三国同盟調印の記念式典と祝賀晩餐会の様子をご覧になってください。ナチスの同盟国となったことを誇らしげに宣言する近衛文麿、独伊大使とともに乾杯をする三笠宮の姿は歴史の教訓そのものでしょう。悪の帝國ナチス・ドイツとの同盟は恥ずべきことです。(
戦後70年 年表:朝日新聞デジタル)また、毎日は朝日より多角的に戦後70年特集を組んでいます。ご覧になっていなかったら、覗いてみてください。(
戦後70年 - 毎日新聞)
ここまで書いて久しぶりにリグミのサイトを開いてみたら、梅本さんの1月6日の新聞解説「戦後80年への第一歩」があり拝読しました。(
2015年1月6日【新聞解説】「戦後80年」への第一歩:LGMI)80年は各紙とも指摘していない概念で「記憶から歴史へ」という見方も新鮮でした。これこそ未来志向、まったく同感です。これからの10年、歴史が評論家や小説家の生半可な知識によるヒストリー(物語)ではなく、プロの歴史家(外国人も含めて)の厳密な検証によるヒストリーが国民共有のものになることが大事だと思います。
「フランスやヨーロッパ諸国には「空気」にあたるものはあるのでしょうか。政治や社会に一定の流れができたとき、それに「水を差す」のを控える雰囲気というのは、ありますか」
現在フランスでは、フランス革命以来の伝統で左右のイデオロギー対立が激しく、勢力も拮抗しているので、右が政権についても左がついても、空気の醸成がむつかしいですね。その結果、実のある改革(とくに経済)ができないように見えます。水の差し過ぎでしょう。しかし、外交方針では右と左の基本的なコンセンサスがあるのは、米国とのちがいです。
自由と民主主義の旗手を自認しているアメリカで、50年代にマッカ―シズムが吹き荒れ「赤狩り」で多くの人びとが犠牲になりました。ブッシュのイラク戦争突入に真っ向から反対した米国の主要メディアはありませんでした。政治家ではオバマなどごく少数が反対しただけでした。いったん空気が醸成されると、どの国でも異論をはさむのは困難です。ですから、汚れた空気の洗浄ができるシステムがいります。それを機能させるのは、権力を怖れない言論機関の役割りだと思います。
昔、親しくさして頂いた大河内一男(労働経済学者、東大総長)さんの著作に「自分のアタマで考える」があります。その内容は、たしか次のようなものでした。
多くの人は自分のアタマで考えていると思っているが、実はそうではない。たいていの場合、誰かが言ったことを繰り返しているにすぎない。人の意見は参考にするが、できるだけファクトを調べてとことん自分のアタマで考えることが大事だ。
これが、汚れた空気清浄の第一歩ではないでしょうか。
土野繁樹
(31)2015.01.24
東京は寒い日が続いていますが、フランス・ドルドーニュ地方はいかがですか。土野さんから年頭の対話をいただきながら、早くも月末となってしまいました。申し訳ありません。
この間、世界は緊迫の度合いを高めています。パリの新聞社襲撃事件は衝撃的でした。メディア関係者のみならず、何らかの形で言論に主体的に関わろうとしている人々にとって、「言論の自由」は根本的なテーマです。何が自由で、どこで制限や配慮が必要か、それ自体が常に言論の対象になるものですが、それが突然に最も凶悪な形で破壊されてしまいました。
テロを容認する要素は一切ありませんし、実行犯たちに同情の余地はありません。がしかし、イスラム教の預言者に対する風刺画がもたらした負のスパイラルについて、「言論の自由」「権力や権威を風刺する権利」という文脈だけで語って良いのか疑問を感じます。フランス全土で起きた反テロリズム運動にも驚きました。フランス人にとって、「自由」は命を懸けて守るもの、という気迫が伝わってきました。同時に、「私はシャルリー」と誰もが語る姿に危ういものも感じてしまいました。
土野さんは、
「現在フランスでは、フランス革命以来の伝統で左右のイデオロギー対立が激しく、勢力も拮抗しているので、右が政権についても左がついても、空気の醸成がむつかしいですね」
と語ってくださいました。なるほどフランスらしいと感心をしました。同じく、
「自由と民主主義の旗手を自認しているアメリカで、50年代にマッカ―シズムが吹き荒れ「赤狩り」で多くの人びとが犠牲になりました。ブッシュのイラク戦争突入に真っ向から反対した米国の主要メディアはありませんでした」
という一文に接し、米国の方が一方的な「空気」が醸成されやすい社会だという実感を私も持ちました。しかし今回の新聞社テロ事件でフランスも一気に「空気」で膨満された感があります。
フランスの作家・哲学者のベルナールアンリ・レビのインタビューが朝日新聞に載りました。パリ5月革命世代を代表する知識人でイスラム過激主義に詳しいと紹介されていますが、同氏は次のように語っています。
「イスラム過激派は、民主主義に宣戦布告しました。それは受けるしかない。テロの源に出向いて、「イスラム国」なりアルカイダをたたくほかありません」
「政治家やメディア、国民はまずテロリズムに対して立ち上がるべきです。方法は無数にある。街頭に繰り出す、シャルリーを買い、脅しをはねのける。特別号は空前の700万部を刷るそうですが、個々のフランス人が負った傷はそれほど深いのです。もちろん『私もシャルリー』です」
あくまで翻訳文なのでニュアンスがわかりませんが、フランス人を勇気づけテロとの戦いに鼓舞する内容に読めます。文中には「愛国的行動のワナにはまってはならない」という表現もあり、国民に冷静に立ち向かうことを呼び掛けていますが、「空気」を膨満させる力感が勝っているように感じました。
(引用:朝日新聞
いっぽう歴史人類学者のエマニュエル・トッドはフランスの「空気」を憂慮する次のようなコメントを読売新聞に寄せました。
「……真の問題はフランスが文化的道義的危機に陥っていることだ。誰も何も信じていない。社会に絶望する移民の若者がイスラムに回帰するのは、何かにすがろうとする試みだ」
「私も言論の自由が民主主義の柱だと考える。だが、ムハンマドやイエスを愚弄しつづける『シャルリー・エブド』のあり方は、不信の時代では、有効ではないと思う。移民の若者がかろうじて手にしたささやかなものに唾を吐きかけるような行為だ」
「ところがフランスは今、誰もが『私はシャルリーだ』と名乗り、犠牲者たちと共にある。私は感情に流されて、理性を失いたくない。今、フランスで発言すれば、『テロリストにくみする』と受けとめられ、袋だたきに遭うだろう。だからフランスでは取材に応じていない。独りぼっちの気分だ」
(引用:読売新聞 1月12日朝刊 「緊急 論点スペシャル」)
トッド氏の悲痛な思いが伝わるインタビューです。でもレビ氏も、内心は同じような思いなのではないでしょうか。みな一様に傷つき、苦しんでいることが伝わってきます。そしてたぶん、世界に15億人いるといわれるイスラム教徒の大多数もまた、深く傷つき苦しんでいるのではないでしょうか。テロと毅然と戦いつつ、テロの原因に分け入り、融和の突破口を作りだすことはできないものでしょうか。そういうムーブメントが起きれば、「シャルリー・エブド」の風刺、そのペンの力は、剣(銃)よりも強かった証明になります。
土野さんが引用された大河内一男(労働経済学者、東大総長)さんの言葉が一層のリアリティーをもって迫ってくる思いです。こういうときこそ、「できるだけファクトを調べてとことん自分のアタマで考えることが大事だ」ということですね。世界は深刻な分断状態にありますが、世界を宥和させようとする地道な努力を続ける人々も確かに存在しています。私はシャルリーではありません。でも人間の本性に信認を置いています。シャルリーと非シャルリーの分断を越える知恵と工夫に希望を見出しています。
きっと今世界は、さまざまな立場の人々がお互いに少しずつ譲歩し、自分の過ちや偏りを認め、そこにできた隙間に相手を招き入れていく努力が必要なのだと思います。そういう意味で、毎日新聞の1/23オピニオン面に掲載された民間シンクタンク「エジプト情勢研究所」研究主幹のアフマド・バン氏の記事「イスラム世界 地位向上を」は、イスラム教徒の多くが自分の利益を優先し、共同体の発展をないがしろにしていると自分たちの問題を指摘しており、新鮮でした。
「(イスラム教徒は)敬愛する預言者のためにも、単に他者を非難するのではなく、自省する姿勢が求められている」
バン氏は記事の結語にこう記しています。イスラム教徒だけでなく、すべての立場の人々へのメッセージだと感じました。
シャルリー事件の衝撃が続く中、今度は「イスラム国」による日本人人質事件が起きました。2つの事件は根っこでつながっているのだと思います。世界を分断する刃が私たち日本人の喉元にも突き付けられました。人質にされた湯川遥菜さんと後藤健二さんが無事に解放されることを願っています。
梅本龍夫
(32)2015.01.30
ドルド―ニュ地方も寒い日が続いています。今朝は庭に霜が降り、隣家の池は凍っていました。ということで、小鳥も餌探しで大変です。いま、朝のお勤め(固くなったパンを金槌で砕いて野鳥の餌をつくる)をして、食堂の窓から見える屋根付きの餌箱に置きました。
�
チャルリー暗殺事件の翌日、ルモンド紙は一面見出しに「フランスの911」と書き、その衝撃の大きさを伝えていました。マスコミはアルジェリア戦争をめぐる連続テロ事件(60年代)以来のショッキングな事件であると言っていました。その後起こった日本人人質事件は、‘イスラム国‘が黒幕と言われるパリの一連の暗殺事件と連動していると思います。
パリの歴史的テロ事件については、次回のフランス田舎便りで「カラシニコフ銃vs諷刺画」のタイトルで執筆中です。このエッセーのなかで、梅本さんの指摘された「表現の自由」「シャルリー空気」について触れますので、しばらくお待ちください。
ここでは、あまり日本のマスコミでは報じられていないフランス人と諷刺画の関係について素描してみましょう。
まずは、フランスの歴史のなかで、諷刺画が果たした役割に触れる必要があります。権力と宗教の偽善の仮面をはぎとる諷刺画の伝統は18世紀にさかのぼります。フランス革命前の諷刺画家は、街の噂をもとにベルサイユ宮殿の腐敗や国王夫妻の滑稽なセックス場面を描きからかいました。この不敬な行為は、アンシャン・レジーム崩壊の一つの要因になったといわれています。
シャルリーエブド紙はこの無礼で下品なスタイルで政治的主張をするジャ―ナリズムの伝統を受け継いでいます。同紙のモットーはタブーなし偶像破壊ですから過激で、ぼくの感覚からすると度を越している作品もあります。同紙にかぎらず、政治諷刺はこの国のジャーナリズムの重要なジャンルです。毒舌(毒画?)のていどは異なりますが、朝のラジオのニュースの前後に政治家を諷刺する番組があります。NHKにあたる公共放送も民間も毎日3,4分やっていますね。
番組を担当する人々はユーモリストと呼ばれ笑いを競い合っています。フランス最高の新聞と言われるルモンド紙の目玉の一つは一面に載っているプランテュのやさしく痛烈な諷刺画です。大統領がその餌食の筆頭です。フランス人は政治的に左翼、右翼を問わず、この種のユーモアが好きですね。フランス革命の末裔である彼らは、腹の底では権威などくそくらえと思っているからでしょう。諷刺は国民スポーツの趣があります。
それにしても、日本の新聞には政治諷刺画がないですね。あっても毒がないから面白くない。日本はマンガ大国なのに、このジャンルでは力を発揮していないのはなぜでしょうね。日本人にはユーモアのセンスがない、と言われていますが、そんなことはないでしょう。ぼくは毎日新聞の万能川柳のファンですが、ここは庶民のユーモアの宝庫です。愚にもつかないお笑いが氾濫しているにしても、日本人は冗談が好きな国民だと思います。
NHKの正月番組に出演したユーモリスト・太田光が担当者から「政治家さんのネタは全然だめ」と言われたと、TBSの番組で語ったとのニュースがありましたが、情けない自己規制です。NHK会長の籾井勝人が「個人名を挙げてネタにするのは品がない」とそれを援護しましたが、これにはあきれました。公人は笑い、諷刺の対象になるのは当然というデモクラシーのルールがなにも分かっていない。知性の香りがまったくしない、こんな人物が公共放送の会長であるのは日本の恥でしょう。彼に比べると、太田光はユーモアという知性がありますね。
政治諷刺がないのは、権力を怖れているからなのでしょうか。NHKはそうかも知れませんが、大新聞は記事では政治批判をしているわけですから、それを諷刺画でやればいいのにやっていない。新聞を面白くするためにも、ぜひスペースを割いてほしいものです。例えば“安部首相、籾井会長を解任、後任は太田光に”というメッセージの諷刺画!
土野繁樹
(33)2015.02.22
東京は少しずつ早春の息吹を感じる瞬間が増えてきました。本格的な春の前に、一番寒い日がやってきたり、大雪が降ったりすることがよくあります。夜明け前が一番暗いという表現もあります。世界で起きているたいへんなことの数々を思うと、寒さに暖かさを、暗闇に一条の光を、という思いを深めます。ドルドーニュの春は近くまで来ていますでしょうか。
パリでの新聞社襲撃事件、中東での日本人人質殺害事件、そしてデンマークでもテロ事件が起きました。今日は、東京マラソンが開催されました。2年前のボストンマラソンでは爆弾事件が起きたことを思い出しました。スポーツは平和の象徴です。平和に競い合い、互いの健闘を称え合える幸福は、ほんらいみんなのものです。参加する人も、沿道で応援している人も。去年は日本橋近辺で見学をしましたが、最初に車いすランナーたちが疾走していく姿にびっくりしました。ほんとうに早いし、かっこよかったからです。障碍があっても、それは乗り越えられる。一陣の風となって吹き抜けていくさわやかさでした。今年も東京マラソンが無事に終わり、良かったです。
土野さんの『
シャルリー虐殺事件 カラシニコフ銃vs諷刺画家』は、その広がりと深さにおいて、出色の記事でした。日本にいては触れることのできない現地の生活感と、世界史の流れの中に「今」があることをあらためて強く認識しました。ただ、あまりに重いテーマが突然日本人にも身近なものとなり、多くの読者はうまく受け止めきれていないように感じます。思いは四方に広がり、茫漠とした心のうちをどう整理したらよいかわからない段階なのかもしれません。それでも、僕らはそれが何か、しっかりと見据え、言葉にしていき、そして行動に変えていく必要があります。
私の仕事の同僚だった知人の女性は、友人の子息の結婚礼拝で司祭が語った言葉、「愛の反対語は憎しみではない。無関心である」を思い出した、と語ってくれました。「とても気が重い、やりきれない、自分では手に負えない気持ち」を乗り越えて、この言葉に到達できたのは、土野さんの記事のエンディングに、ローマ教皇フランシスの発言を引用し、「筆者も表現の自由は絶対ではないと思う」と結ぶ文章を目にしたからでした。
「最後の、表現の自由は他人の信仰を侮辱するものであってはならない、に改めて大きくうなずき、少し救われました。どの宗教の原典も、愛がなくては人は生きていけず、愛は寛容であり情け深く裏切らない、はず」
知人のこの言葉に同感します。
昨日、日本で公開されたばかりの映画『アメリカン・スナイパー』を見ました。もうすぐ85歳になるクリント・イーストウッド監督の最新作(!)は、イラク戦争で160人以上を射殺した「伝説」の狙撃手クリス・カイルの半生を描いたものです。一言で批評することがむつかしい映画でした。実際、米国でも評価が二分されているようです。リベラル派は否定し、保守派は称賛する、という図式で。
おそらくイーストウッドは思想的には筋金入りのタカ派ではないかと思います。しかし同時に、彼は人を殺すという行為が、どのような経緯で行われたとしても、人の心を壊す恐ろしく罪深いことであることを、どの映画監督よりも深く感じているのではないかとも想像させられます。だからでしょうか、この映画は、国威発揚映画でなく、反戦映画でもない、という立ち位置にあり、しかし中立ということでもなく、いわば観客が自分の主観において「それが何か」を決めていく作品に見えます。
イーストウッドには、『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』という映画史に残るユニークな連作があります。太平洋戦争で日本の敗戦が濃厚になっていた1944年に硫黄島に米軍が上陸。そのときの様子を、2つの映画は正反対の立場から描写しました。僕は両作品を見て深く心揺さぶられました。『アメリカン・スナイパー』に決定的に欠けているものがあるとすれば、この対極視点ではないかと気づきました。
『アメリカン・スナイパー』では、イラク人は「野蛮人」であり「テロリスト」であり「自分たちとは異質で理解できない存在」のように描写されています。それが狙撃手クリスの視点だったからです。だから彼は160人もの人殺しを実行できたのかもしれません。しかし、その結果、戦場中毒のような状態になり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しみます。イーストウッド監督であれば、そのときイラク人たちもまた、激しい心の痛みの中にいたことを、きっと静かに描写できるでしょう。そんな連作を観たい気がします。
イラク戦争は、911をきっかけに米国が仕掛けましたが、今では両者に関係はなかったというのが定説です。そして、「イスラム国」(IS)という名の武装勢力が台頭したのは、米国が仕掛けたイラク戦争が原因だとする説が強く主張されています。それは正しいのだと思いますが、ほんとうの原因は911のはるか前にまでさかのぼる必要があるのではないでしょうか。おそらく第一次世界大戦前後の欧州列強による中東政策に。ただ浅学非才で事実もよくわかっていません。このあたりは、土野さんの「次回作」で是非、深堀りしていただけたらと希望するテーマです。
最近読んだ経営戦略解説本にイラク戦争のことが描写されていました。米軍は、イラク戦争の大規模戦にはすぐに勝利しましたが、その後の統治に失敗し、犠牲者を出し続けました。そこまでは良く知った話だったのですが、ラムズフェルド国防長官の更迭後に、イラクの統治現場に変化が起きたことを知りました。
テロリスト殲滅をめざしていた米軍は、「対ゲリラ戦の核心は、ゲリラの殺害ではなく、民心の掌握である」と気づき、それを対反乱作戦マニュアルにまとめました。新しいマニュアルの根幹に「イラク人への敬意」が置かれました。現地で指揮にあたった新しい米軍将校たちは、イラク入りする前からイラクの歴史本を読み漁り、現地でどう行動すべきか考え抜いていました。そして「イラク人に無礼な態度をとることは、敵を助けるということだ」と兵士たちを説き続けました。その結果、イラクの民心は変化し、自律的な治安維持への一歩を踏み出しました。それまで月2500人だったイラク民間人死傷者数は500人前後に減り、月100人程度だった米軍死者数は10~20程度になりました(以上、参照:三谷宏治著『経営戦略全史』pp.341-353)。
この世に野蛮な行為はあっても、野蛮人はいない。相手に関心をもつ。敬意をもって接する。そこから理解が始まり、大事な一歩を踏み出せる。互いの痛みを共有できたとき、ほんとうの勝利への道が見えてくる。イラク戦争の「その後」を知って感じたことです。「今」が夜明け前であることを願っています。
梅本龍夫
感想をお待ちしております。
アーカイブ