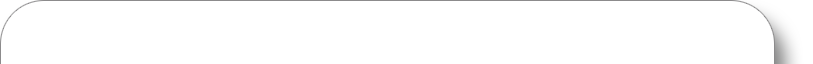ピケティ氏は日本でも注目されていますが、このエッセーほど世界の現状(背景)を深堀したうえで人物像を浮き彫りにした記事は見かけません。日本人にとって貴重な情報になると思います。
あらためて問題意識を持ったのは、新自由主義的な政策の是非です。規制緩和をし、自由競争を促進し、突出した「アメリカンドリーム」を実現すれば、その余得が残りの人々にもこぼれ落ち、全体を底上げするとする理論(仮説)の有効性です。非常に刺激的なテーマです。
日本はトップ1%の富の集中が9%とのことですが、かつて平等性の高かった日本社会でも、一部の富裕層が着実に増えている実感はあります。米国がトップ1%で20%の富の集中ということですので、これに比べればマシなのでしょうが、米国と違い、富の集中がもたらすインパクトは、日本の方がダメージが大きいのではないかと思います。
エッセーを拝読し、30年前の米国の富の集中度は、トップ1%が8%を所有していたと知り、現在の日本と同程度だったことに感慨を覚えました。30年前といえば1984年であり、私が米国スタンフォード大学に留学していたごろです。当時の米国は、今の日本よりも富の還流が大らかになされていたように感じます。アメリカンドリームを体現した人を称賛する一方で、成功者は次の成功者を育てる活動をしたり、恵まれない人々を助ける社会貢献などに積極的だったように見えました。
日本は、本当の金持は、地味に生活し目立たないようにしているといわれます(日経ビジネスの特集記事など参照)。その結果、富の還流や社会貢献といったダイナミックな社会の動きも、そがれているように思います。また、大学を出て正規雇用につけないと、ずっと非正規雇用の立場にとどまらざるを得なくなるなど、格差が固定化する硬直的な社会になっています。経済活動が生む過剰な格差を問題にすることは当然必要ですが、日本の場合はむしろ、格差の固定化を解消する発想が必要な気がいたします。
そんな日本は、漫画『ONE PIECE』が累計3億1千万部売れる社会です。「仲間」「信頼」「約束」といったキーフレーズがこの漫画の世界観の根底にあります。若者たちは富の集中と格差の固定化とは異質な社会に、理想を見出しているのではないでしょうか。格差の少ない社会でも創造性が高く、わくわくする楽しさと、安心感が同居することは可能ではないか。むしろそのほうが全体としてしあわせなのではないか。私は今そう感じています。
文学では、ドストエフスキー著『罪と罰』を高校生になったばかりのときに読み、小説世界の醍醐味と人間洞察の深さに大いに感銘を受けたことを今も鮮明に記憶しています。ロシア語を読めるようになる可能性はほぼゼロであったことを思えば、豊かな翻訳文化の国に生まれ育ったしあわせを実感した瞬間でした。『21世紀の資本論』はみすず書房が版権を取ったそうですが、翻訳本を手にするのが楽しみです。
梅本龍夫
(10) 2014.07.10
ご感想ありがとうございます。
この書評を書いていて、二つのことに気づきました。日本ではアベノミクスによる成長論は話題の中心ですが、富の分配は語られませんね。格差は話題にはなるが、エコノミストの再分配の提案にはお目にかかられない。なぜでしょうか。ピケティは世襲資本主義への警鐘を鳴らしていますが、米国ほどの富の集中がない日本はイエローカードくらいでしょうか。しかし、日本の世襲政治家による権力の集中はレッドカードではないでしょうか。この弊害はいまやピークに達していると思います。ちなみに、戦後の英仏独の首相や大統領のなかに、2代目や3代目は一人もいません。
日本における格差の固定化は重要なご指摘だと思います。格差の固定化の究極のかたちは徳川世襲政権下の士農工商ですが、現代版の最下層は日本の労働人口の40%を占める契約社員とパートでしょう。今日、読んだガーディアン紙によると、英国の契約社員とパートは25%ですから、この国を凌いでいることになりますね。この層の固定化をどう回避するかは、政策立案者の大きな課題だと思います。
フランスの格差をどう思うか、との質問にお答えします。ピケティの本が昨春パリで刊行されたとき、ほとんど注目されませんでした。米国でベストセラーになったあと、この本がよく売れています。なぜ、本国で当初は関心が薄かったかは、不平等への関心がフランスでは高いからだと思います。労働組合が強く(最近でもフランス国鉄が1週間のストを打っています)、TVも新聞も不公平、不平等には神経を尖らして報道していますね。フランス革命以来の伝統ですね。
ピケティが出演したCNNの番組で、司会者は「これを見ている視聴者の皆さんは あの平等だった50年代に戻りたい、と思っている」と言っていました。事実、当時は 経済成長率が高くそれに応じて生活も向上する時代でした。格差はあったにしても、中産階級にとってベル・エポックだったといえます(黒人層10%は別ですが)。米国がいまのような格差社会になったのは、30年前のレーガン大統領の金持優遇税制に端を発していると思います。彼が唱えるトリックル・ダウンは幻想でした。
ピケティの本の書評をしたのを契機に、カール・マルクス伝“Karl Marx”Francis Wheen著(1995年)を読んでいます。ジャーナリストである著者がその「人と思想」の軌跡を鮮明に描いている優れた本です。さすが伝記王国の英国、読ませます。
マルクスがワインと葉巻と冗談が好きで、妻の家系はプロシアの貴族で祖父は参謀長、亡命先のパリとロンドン(34年間)での借金だらけの家族5人の貧乏(ときに極貧)暮し、マルクスを物心両面で支えたエンゲルスの友情、ニューヨークの新聞の特約記者10年の体験・・と「これまでマルクスについてなにも知らなかった」と思いながら読んでいます。彼は後世に害をまき散らした怪物ではなく、産業革命が生んだ不平等の要因解明を試みた偉大な思想家であったことを学んでいます。
われらが潤二郎先生、コンラート ローレツ著『ソロモンの指環―動物行動学入門』、エドワードTホール『かくれた次元』とはさすがですね。『罪と罰』を高校時代に読まれたのにも敬服です。先生健在なら、ピケティの本についてのセミナーを開きたいところです。
『21世紀の資本論』はみすず書房から12月に山形浩生さん訳で刊行されます。
土野繁樹
(11) 2014.07.15
「ニューズウィーク日本版は、翻訳の質が勝負の雑誌でした。英語の記事を早く正確に訳しかつ読ませる日本語にするため、たしか5工程を経て、最終稿にしていました」という一文に接し、翻訳とは本来、ひとつの作品を一から作り上げることに匹敵するものなのだと思い知りました。
あと、「いい翻訳ができる人は、英語力、内容の理解力、日本語力が同等にあると思います。原作が面白くても、訳者に日本語力がないため、魅力のない本になっている例が世のなかには一杯ありますね」という一文にも注目しました。土野さんのエッセーは翻訳ものではありませんが、今回のピケティの『21世紀の資本論』のように、まだ翻訳が出版されていない本を私たちが立体的に理解できるのは、「英語力―内容の理解力―日本語力」の三角形のバランスが良いからなんですね。今、「大学教育を英語で」という流れがありますが、これだけでは学生たちの三角形は崩れたままでしょう。
これは早川書房の編集者から聞いた話ですが、レイモンド・チャンドラーの翻訳を手掛けた清水俊二氏は、映画字幕の仕事を長くしてきたため、かなり文章を切り詰めた意訳になっているのに対し、チャンドラーの文体の影響を受けた村上春樹氏の新約は、原文に忠実な翻訳になっているそうです。たとえば‘The Long Goodbye’は、清水約のタイトルが『長いお別れ』であるのに対し、村上約は『ロング・グッドバイ』と原題通りなのも象徴的です。どちらのチャンドラーがより魅力的なのでしょうか。私は読んでいないのでコメントできませんが、ファンの声を聴いてみたい気がします。
翻訳といえば、公開対話(7~8)で話題になった『赤毛のアン』の翻訳者、村岡花子について、菱田信彦著『快読「赤毛のアン」』という本が出版され、毎日新聞に書評が出ていました(6/29)。書評子は、「彼女は、時に大胆すぎるほど自由に原作を離れ、日本の『アン』を創作していく。でも、そのおかげで私たちは、雑念なくアンの物語を自分の冒険として生き、これから始まる自分の人生に思いをはせることができた」と記しています。
ここで、少々難題だなと感じることが出てきます。正確な翻訳がなされなければ、私たちは原文に記された「事実(FACT)」を知ることができません。しかし、創造性を発揮する意訳を通して、私たちははじめて作品に込められた「真実(Truth)」を体験できるのではないでしょうか。
ある哲学書を読んだ体験で言うと、その哲学者の弟子にあたる方が日本語訳をした本をまず読みました。知識として自然に読める内容で、理解が進む実感がありました。ところが英語の原書をひもとくと、著者の格調高い文体に魅せられ、精神性の深さに感銘を受けました。そこで、もう一度翻訳本を読んでみました。原書と比較して、間違いや省略があるわけではありません。むしろ、できるだけ正確に、そして平易に訳した優れた仕事であることがわかりました。それにもかかわらず、作品から受ける感銘のレベルは到底及びませんでした。
とはいえ土野さんのように英語やフランス語の文献を自由に読むことは到底叶わないので、良い翻訳本に巡り合うことは、とても大事なことです。「カール・マルクス伝」を原書で読まれているとのこと、初めて聞くマルクスの人物像が新鮮でした。こちらの翻訳本はあるのでしょうか。ピケティの『21世紀の資本論』の翻訳は12月には出版とのこと、楽しみです。
梅本龍夫
(12) 2014.07.19

ぼくの編集者人生のなかで、何人かの一流訳者に出会いましたが、そのなかで最も印象に残っているのが、上智大学の教授だった安西徹雄さんです。彼はシェークスピア学者で、劇団円の演出家で、ぼくの『ブリタニカ国際年鑑』(翻訳70%書き下ろし30%)編集長時代のスター翻訳者でした。毎年、巻頭に特別寄稿を3,4本掲載していたのですが、いつも目玉になる記事を担当してもらっていました。
ホメイニのイラン革命を覚えてます?パーレビ皇帝を倒してイスラム共和国を樹立したあの1979年の革命です。筆者はホメイニをインタビューし、イラン革命を取材した女性ジャーナリスト・アン・ゲイヤー。彼女の臨場感あふれる優れた分析記事を、流れるような日本語で見事に安西さんが訳してくれました。原文の記事を正確かつ読み物に仕立てる小柄であごひげの安西さんのことを、編集部では知的スケールが大きい人との敬意をこめて「小さな巨人」と呼んでいました。今では故人となった彼が訳したサイデンステッカーさんの『東京・下町山の手』は名訳です。
良い訳はいい香りがしますが、悪い訳は息がつまります。不自然で、ザラザラして、流れが悪く、途中で投げ出したくなる翻訳書がそれです。大学教授の訳書にこの種の本が多いですね。たいていの場合、日本語力の不足からきています。エッセー30でとり上げたウィンストン・チャ―チルの『第二次大戦回顧録』の邦訳は、ジャーナリスト出身の有名な訳者の仕事ですが、粗っぽい仕事でチャ―チルも読者も気の毒です。良い訳書もある人でしたが、拙速にすぎました。
良い訳のバロメーターの一つは、原書にある意外な視点、新鮮な表現がうまく訳されているかでしょう。それもいい香りがするかどうかの分かれ目になりますね。いずれにせよ、翻訳は「英語力―内容の理解力―日本語力」の三角形のバランスが基本だと思います。
レイモンド・チャンドラーの‘The Long Goodbye’のタイトル、清水俊二訳は『長いお別れ』、村上春樹訳は『ロング・グッドバイ』、どちらも分かるような、分からないようなタイトルですね。ずいぶん前にこのハードボイルド小説を英文で読みましたが、内容よく覚えていません。読みながらハンフリー・ボガードの顔がちらついたのは覚えていますが。村上春樹のお手並み拝見したいですね。
先週末に、早川書房からキャロライン・ケネディが選ぶ「心に咲く名詩115」の寄贈を受けました。シェークスピア、チョーサーから現代詩人まで名作が、柳瀬尚紀さんの訳で紹介されています。柳瀬さんの素晴らしい訳に感嘆しました。たとえば、「戦争の苦悩」詩集のなかに収録されたバイロンの「センナケリブの破滅」(137ページ)は傑作訳だと思いました。ケネディさんのまえがきと解説も見事!知性が輝いています。
Francis Wheenのマルクス伝の訳は残念ながらでていません。
土野繁樹
(13) 2014.07.24
ホメイニのイラン革命はよく覚えています。1979年と言えば、私が社会人になった年。1970年代は中学、高校、大学と重なった時代で、戦後の高度成長が終わり、新しい消費社会に移行する生活者の感覚を、学生なりに感じていました。特に、1973年の第1次オイルショックは、トイレットペーパーがなくなる社会現象が起き、いろいろな意味で大衆消費社会の基盤のもろさを実感しました。そして1979年に、イラン革命を契機とした第2次オイルショックが起きたのでしたね。
イラン革命は米国の傀儡政権と言われたパーレビ王朝を倒し、イスラム教に基づく統治に移行した、まさに「革命」でした。米国を中心とする西洋先進国にとって都合のよかった中東の治安体制が崩れ、今日につづく混乱の端緒になったのがイラン革命だったのではないでしょうか。経済を支える石油の大半を中東に依存する日本にとっても、パーレビ王朝が続いた方が都合がよかったのだと思います。しかし今から振り返ると、民衆が独裁や帝国主義に抗していくのは、世界史の大きな流れであったことがわかります。
イスラム教に対する西洋諸国の忌避感や嫌悪感は大きいと思いますが、そのひとつの端緒がイラン革命にあったのかもしれません。しかしいつも不思議に思うのは、イスラム教とキリスト教は、同じルーツをもつ一神教にもかかわらず、なぜこうも反目しあうのかということです。十字軍のエルサレム遠征の時代からつづく歴史の堆積物のなせることなのでしょうか。イスラム教徒との共存の問題をフランス人やEUの人々はどうとらえているか、フランス在住の土野さんからご覧になっていかがでしょうか。
日本にいると、中東問題はもっぱら経済問題(石油の安全保障)になりがちです。集団的自衛権の議論で自衛隊がペルシャ湾の機雷除去をするという想定も、同じ構図です。イスラム原理主義の問題も、テロの問題も、経済だけでなく、グローバルな政治と社会の問題としてとらえることが、日本の「平和主義」をほんものにしていくのだと思います。武力に依存しない日本の力量が問われている。イラン革命を思い出し、そんな感慨が湧きました。
ところで、今週号の「週刊東洋経済」は「『21世紀の資本論』が問う 中間層への警告」という特集記事を掲載しています。巻頭のピケティのインタビュー記事は興味深かったです。土野さんのエッセー(『21世紀の資本論』の衝撃
http://lgmi.jp/detail.php?id=2200)でピケティの人物像や著書の概要を予習できていたので、インタビュー内容をよく理解できました。執筆の動機のひとつに「学問の分類上の問題」(“経済学者にとってはあまりに歴史的すぎる、歴史学者にとってはあまりに経済学により過ぎている。だから誰もやらなかった”)があったという話は面白かったです。
格差の問題をどうとらえるかは、ピケティの問題意識、思想の根幹と深く関係しているのですね。資本主義は格差を助長し、民主主義は格差を是正する。経済を成長させ、人類に物質的豊かさをもたらすのが資本主義の効用だが、真に人類にあまねく経済成長の恩恵を行き渡らせるのが民主主義の役割。こんな感じでしょうか。資本主義の自由度を重視するか、民主主義の縛りを重視するか。経済政策に関する基本スタンスの違いは、思想的にはけっこう深い溝になっている感じがします。
ちなみに、ピケティをマルクス主義者ととらえる見方に対して、「私は資本主義を否定するつもりはない。民主的な制度により、きちんと管理されるなら、もちろん受け入れる」と答えていますね。ただ、ピケティの思想は「資本主義を下部構造、民主主義を上部構造」ととらえているように見えます。下部構造と上部構造の弁証法的なダイナミズムを、マルクスのような硬直的で機械的な理論ではなく、もっと柔軟で生物学的な理論に発展させていくと、ほんとうに「21世紀の資本論」になっていくのではないかと感じました。
ブリタニカ時代の土野さんのもとで、安西徹雄さんがホメイニ師のインタビュー記事を翻訳していたのですね。「知的スケールが大きい人との敬意をこめて『小さな巨人』と呼んでいました」というお話、印象的です。
公開対話(7~8)で「反知性主義」が話題になりましたが、日本の政治・社会がこうした言葉に象徴されることを憂いています。「21世紀の小さな巨人」がたくさん現れてくれることを願っています。
梅本龍夫
(14) 2014.08.06

暑中お見舞い申し上げます。
返信遅くなり失礼しました。この1週間、次のエッセーを書くためにノーベル賞作家の小説を読んだり、友人から頼まれた翻訳のリライトをしたり、庭の草むしりをしたり、コンサートに出かけたりで忙しくしていました。お手元に原稿を送り一息ついて、クラッシック音楽専門ラジオ局Radio Classicでシューベルトを聞きながらこの返信を書いています。
ご指摘のようにホメイニのイスラム革命は、現代史の分水嶺でしたね。米国のベテラン海外特派員Christian Carlが書いた”Strange Rebels:1979 and the Birth of the 21Century(2013)ご存じですか。この本のテーマは、1979年の3つの出来事が、現代世界を動かしている震源地だというものです。ホメイニ革命によるイスラム宗教勢力の台頭、サッチャー革命による新市場経済の出現、鄧小平の「4つの現代化」による中国の世界舞台への復帰がそれです。面白い見方ですね。書評を読んだだけなので、いずれ読んでみたいと思っています。
ヨーロッパとイスラム教の関係、大きなテーマですね。イスラム教徒移民の同化、アラブ圏からの不法移民の問題はフランスだけでなく、他の多くの欧州諸国の共通な主要課題です。これ、機会があればエッセーで取り上げたいと思っています。
ダイヤモンド誌のピケティ特集お送り頂きありがとうございました。インタビュー記事のなかで、彼が「資本主義には道徳的規律がない」と言っていますが、これは核心をつく指摘ですね。新自由主義の信奉者はこのことに気付くべきでしょう。ピケティの本をテーマにNHKで2時間の特集番組をやったようですが、この点がどこまで論じられたか興味あります。
ピケティの思想は「資本主義を下部構造、民主主義を上部 構造」ととらえているように見えます。
この分析は面白い!共産主義は、下部構造(経済システム)が民主主義を確立するはずが、独裁主義をつくりだしました。現代の資本主義は、民主主義を弱体化しつつあるというピケティの分析当たっていると思います。
執筆の動機のひとつに「学問の分類上の問題」(“経済学者 にとってはあまりに歴史的すぎる、歴史学者にとってはあまりに経済学により過ぎている。だから誰もやらなかった”)があったという話は面白かったです。
この発言、ぼくも面白いと思いました。スミス、マルクス、ケインズにつながる政治経済学の復活宣言ですね。経済学が数学の奴隷になったような状況を、ピケティは「数学への異常なこだわり」と言いからかっています。また「フランスでは経済学者の地位は高くない。テレビに出演するコメンテーターは、哲学を専門にしたような人々が生半可な知識で経済を語っている」と言い、哲学偏重のフランスの知的風土に批判的です。彼自身は、自分は世間でいうエコノミストの範疇には入らないと思っているようです。
反知性主義といえば、その権化のような男、NHK新会長に公共放送は牛耳られているようですね。新宿の焼身自殺事件を報道せず、クローズアップ現代の菅インタビューに詫びをいれるは異常です。NHKに幹部は、なぜゲリラ戦を挑まないのでしょう。
土野繁樹