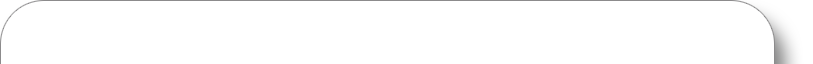(1) 2014.06.05

土野繁樹様
「
ノルマンディー上陸作戦の舞台裏」を拝読しました。3冊の歴史書を読み込まれた上でのエッセーだけに、ストーリー性(ドラマ性)と史実が織りなす妙に惹かれ、一気に読みました。
史上最大の作戦は、その名のとおり、圧倒的な物量でナチス・ドイツを攻めあげた連合軍のイメージがありました。しかし、背景にはこのような激しい情報戦があったのですね。まるでスパイ小説か映画を見るようで、驚異的でした。
ガルボという二重スパイの存在が歴史を変えたということを今回のエッセーで知りました。ファシズムを嫌うひとりの青年が正義を求めて、組織に対して不義を重ねていく姿は圧巻です。二重スパイという役割を果たせる精神は、ふつうではないと感じました。
「ダブル・エージェントが敵対する二つの国から、勲章をもらった例はかつてない。」という一文に、ガルボの際立った力量とタフネスが凝縮されています。戦後にドイツ情報部の工作指揮官が鉄十字章をガルボに渡したというエピソードも実に印象深いものがあります。戦後も偽装は続いたのですね。そのときガルボはどのような気持ちだったのでしょうか。
「戦時においては、真実はあまりに貴重なので、ウソのボディガードで守らなくてはならない」というチャーチルの言葉は、重いものがあります。戦後、真実が明らかにされていくことで、歴史に学べる私たちは幸せです。とりわけ中国で真実が覆い隠される天安門事件25周年の今、大事なメッセージと感じます。
ところで、情報戦に負けたナチス・ドイツ側の当事者たちは戦後、どのような歴史の検証をおこなったのか、あるいはおこなっていないのか、気になりました。歴史の真実は、両側から光を当てることで一層立体化するのではないでしょうか。
硫黄島の戦いを描いたクリント・イーストウッドの2つの映画『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』は、同じ戦闘場面を、2つの映画で日米の両側から描くことで、戦争の真実が立体的に浮上する体験となりました。
日独伊三国同盟とは何だったのか。連合国の戦勝歴史検証に対して、同盟側の敗戦歴史検証もできるようになれば良いですね(すでにあるのかもしれませんが)。
ガルボが、アルゼンチンで別人として生き続けたところを晩年に英国に戻り、ノルマンディーを訪れる。このラストの簡潔な描写を通して、ガルボという暗号名が、忘れることのできないものとなりました。
梅本龍夫
(2) 2014.06.07
ご感想ありがとうございます。
まずは、今日のノルマンディ上陸70周年記念式典の実況中継のことを報告しましょう。日頃はあまりTVを見ないのですが、朝はFrance2、午後はBBCを6時間も見ていました。それでもちゃんと日課の庭仕事2時間はやりました!
以下、印象に残った場面です。
ア メリカ兵の墓地(1万人が眠る)近くで行われた式典でのオバマの演説のなかに「アメリカの若者は知らない人のために命を捧げた」という一節がありました。知らない人 というのは、アメリカ人ではなくヨーロッパ人を意味していますが、”彼らはナチスの圧政からヨーロッパを解放するという大義を信じて戦った。自由という 普遍的価値を守るために死んだ”とオバマは言いたかったのだと思います。オランドは「フランスは、この国を解放する戦いで亡くなったアメリカの若者の ことは決して忘れない」と語っていました。
各国首脳が出席した式典で、メルケルが入場してきたときには大きな拍手がありました。60周年記念のときに、初めてシュレーダー独首相が招待されたのですが、そのときに比べて温かいとBBCはコメントしていました。
式典の最後に、70年前に敵味方に分かれて戦い、戦後に友人となったフランスとドイツの元兵士、いまでは90歳の二人が抱き合う場面がありました。この和解を象徴するシーンは感動的でした。
メルケルがプーチンとウクライナの新大統領と会場で立ち話をしている場面の映像をBBCが流していました。記者は「70年前ノルマンディは歴史を変えたが、今でも歴史を変える力をもっているかもしれない」とウクライナ危機が回避されることを示唆しています。
France 2の軍事ジャーナリストがガルボに触れ、BBCのニュースで軍事史家がノルマンディ作戦はギャンブルだったと言うのを聞いて、今回のエッセーのテーマが確認でき嬉しく思いました。
日本のノルマンディ報道いかがでしたか。
土野繁樹
(3) 2014.06.09

ノルマンディー上陸70周年について、私の知る限り、日本の報道は限定的でした。テレビはほとんど見なかったので、新聞の印象についてだけですが、内容は以下のようでした。
「G7の直後に首脳たちが場所を移動してノルマンディー上陸70周年の式典に臨んだ」
もちろん実際の記事はもっといろいろな情報が盛り込まれていたのですが、印象としてはあまり中身がなかったのです。たぶん同じ第二次世界大戦でも欧州戦線は遠くの出来事であり、歴史的意味を当事者として感じ取っていないのだと思います。
G7の報道に関しても、ロシアがからむウクライナ問題は欧州各国と米国の主要な関心事でしたが、安倍首相が主張した中国の海洋進出問題は「ついでの扱い」だったのではないでしょうか。欧州から見て、アジアの緊張は懸念ではあるが、ちょうど日本から見たウクライナのように見えるのではないでしょうか。中国との経済関係が大事という現実問題もあるのかもしれませんが。
そんな中、土野さんのエッセーは、欧州の視点を日本人の目で拾い上げ、私たちのわかりやすく伝えてくれるので、たいへん参考になります。読者の方からもそのようなコメントを頂いています。たぶん「グローバル化」という時代の言葉がこれだけ一般化した今も、実際の目線は欧州も米国も日本(アジア)、それぞれローカル発なところが依然として主なのだと思います。
そんな中、今回のエッセーでガルボの存在を知り、「ノルマンディー上陸作戦はギャンブルだった」ことを知ることができたのは大きな意味がありました。「アメリカの若者は知らない人のために命を捧げた」というオバマ大統領の演説のメッセージや、独仏の元兵士が和解するシーンの話をさらに伺うと、これは過去の話ではなく、現在進行形の物語なのだと気づかされます。
「もしギャンブルに失敗していたら歴史はどうなっていたのか?」
歴史にIfはないと言いますが、歴史から学びを得るためには、Ifを問うて「現在の基盤の重み」を知る必要があるのかもしれないと今回感じました。土野さんは「歴史から学ぶ」ために、どのようなことを大事にされているのでしょうか。
梅本龍夫
(4)2014.06.11
「歴史から学ぶ」ために、なにを大事にしているのか?
ぼくの場合、まずは信頼できる本を見つけることです。ノルマンディ上陸作戦をテーマにすることを決めて、すぐに映画「史上最大の作戦」の原作を読みました。著者のライアンは英国の従軍記者としてノルマンディ作戦を取材し、1000人の関係者の協力を得て書いた本ですから、人間ドラマのドキュメンタリーとしては最高でした。(戦後、ロンメルの副官に取材して、ロンメルの妻への誕生プレゼントの靴のサイズまで描かれています!)
しかし、ライアンの本は1958年の刊行ですから、その後の新資料、証言、研究を基にした歴史家の本があるはずだと思い、インターネットで調べ見つけたのがAntony Beevor著“D-Day”(2009年)です。軍事史家としては定評のある人で、書評を読みアマゾンで一章を試読しすぐ買いました。500頁の大著ですから、200頁を読んで参考にしました。「作戦の成功は保証されていたという人々がいるが、彼らは現実を知らないArmchair historian(安楽椅子・歴史家)である」と言い、それを実証しているのに共感を覚えました。
今回のエッセーの核になったガルボのストーリーは、はじめは視界に入っていなかったのですが、いろいろ調べるうちにこれは凄いと思い、3冊目の本Ben Macintyre著 “Double Cross “2012刊をアマゾンで入手しました。リグミ編集部へ原稿を送った時点では、一部だけ読んでいたのですが、昨日読了しました。ガルボを含めた5人のMI5のダブル・エージェントの大偽装工作を描いた実に面白い本でした。
3冊の本とも詳しくソースを明記しているので、書かれていることの裏付けがあります。 “Double Cross“の著者はTVインタビューで、彼がこの本を書けたのは、「英国の情報公開法で公になったMI5の文書のおかげである」「ガルボについての文書は高さ1メートルもあった」と言っていたのが印象に残っています。事実、脚注(Notes)を見ると、情報機関の文書が頻繁に使われています。ダブル・エージェントの会話引用の部分のソースとしてMI5の文書が明記されているので、英国の情報公開の透明度が高いことがわかります。
「歴史から学ぶ」ためのぼくの体験的第一条件は、書き手が信頼できるか、事実が正確であるかです。Comment is free but facts are sacred(コメントは自由である。しかし、事実は神聖である)。これは1821年創刊の英国のガーディアン紙の初代編集長の言葉です。
昭和史の第一人者、半藤一利さんが「秘密保護法が成立すると、歴史家は本が書けなくなる」と語っています。この法案がなくとも、官民ともに隠ぺい体質が強い日本では、事実が国民の前になかなか明らかにされません。安倍内閣の歴史感覚はきわめて歪な上、歴史は国民の知的資産で、不都合な真実も含めて次世代に語り継ぐものだ、という認識が希薄なようです。このままでは、日本国民ますます歴史音痴民族になるのではと危惧しています。
土野繁樹
(5) 2014.06.16
土野さんのエッセーは、過去の体験や既にお持ちの知識に依存せず、テーマに沿ってかならず文献調査をされていることには気づいていましたが、あらためて「歴史から学ぶ姿勢」の要諦を学んだ気がします。
「ノルマンディ上陸作戦の舞台裏 ~フランス田舎暮らし(34)~」(
http://lgmi.jp/detail.php?id=2169)で参照された3冊の本、とりわけベン・マッキンタイアの著作’ Double Cross: the true story of the D-day spies’(『裏切り―D-デイのスパイたちの真実の物語』)の内容が印象的でした。「今回のエッセーの核になったガルボのストーリーは、はじめは視界に入っていなかった」とのことですが、事実をつまびらかにしようとする基本姿勢があることで、こうした秘史が浮上してくるのですね。一読者としては、「歴史に学ぶ」醍醐味を味わいました。何よりも面白く、わくわくしました。ガルボを主人公にした本格的な映画を制作する話はないのでしょうか。
核兵器が大量に存在し続ける今日の現実に対する認識を根幹から揺るがした前回のエッセー「原爆事故、ニアミスの恐怖 ~フランス田舎暮らし(32)~」(
http://lgmi.jp/detail.php?id=2012)では、アメリカ人ジャーナリスト、エリック・シュローサーの著作“Command and Control:Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety” 2013年刊(『指揮と統制―核兵器、ダマスカス事件、そして安全幻想』)が圧倒的な迫力で迫り、文字通り背筋が凍る思いでした。こちらはドキュメンタリー映画があると、より広く人々に真実が広まるのではないかと思いました。
ここ数年で日本の言論は大きく変質してきているように感じます。Comment is free but facts are sacred(コメントは自由である。しかし、事実は神聖である)という英国ガーディアン紙の初代編集長の言葉が重く響きます。意見や考え方は違って良いと思います。多様性は貴重な価値です。ただ、両極端な意見であっても、拠って立つ「事実」は同じものを共有できるのが理想なのですが…。歴史はいうまでもなく過去の事実の積み重ねなのですが、実際には歴史の多くは事実の解釈であり、認識の仕方であるために、「何が事実か」が論争の種になりがちですね。残念なことです。いっさい解釈を加えない事実のデータベースづくりだけを行う客観的な機関があればと思ったりします。
ところで、「歴史から学ぶ姿勢」は文献調査が基本ということはわかったのですが、どんな本や資料でも良いわけではなく、まさに土野さんも「信頼できる本を見つける」とおっしゃっています。これは簡単のようで、実は多くの人にとってむつかしいことなのかもしれないと思ったりします。好みに合う本、興味を引く本、他人が薦める本は、見つけられます。でもそれが「信頼できる本」といえるためには、もっと何かが必要な感じがします。土野さんは、直観で選ばれるのですか?それとも、何か客観的な基準をお持ちなのですか?
あと、今回の著作‘Double Cross’のように、「信頼できる本」の少なくない候補は日本語になっていない文献だと思います。英語ができること、英文を読むことをいとわないことも大事なのでしょうね。ただ、英語の本を読める人は日本では限られます。これも、日本の特徴でしょうか?フランスなどはどうなのでしょうか?あと、日本は翻訳文化の国であり、良書が翻訳される可能性もあると思うのですが、それでも原書で読むのとは違いのだと思います。このあたりのご経験やお考えもお聞きしてみたく思います。
しかし…考えてみれば、日本の最近の言論の変質や、ネット上などでの人々の発言内容の変化は、「本を読まなくなったこと」と関係しているのかもしれません。昔から、井戸端会議や居酒屋談義はありましたが、今ではそれがネットなどの開かれたメディアで拡散していきます。私たちのこの「公開対話」もネットの活動ですが、時にはIT端末を閉じて、良質な書を一冊小脇に抱え、街に出る。あるいは旅に出る。そして世界の在り方について静かに考えてみる。それが今必要な小さな一歩という気がします。
梅本龍夫
(6) 2014.06.20

あの素晴らしい1944年の夏
信頼できる本をどのようにして見つけるか?
この季節、連日庭仕事をやっています。今日は、薔薇と水仙の周りの草むしりを無念無想で2時間やりました(汗がでるので休憩4回!)。けっこういい運動になります。
シャワーを浴びてすっきりしたところで、お答えします。まずは「原爆事故 ニアミスの恐怖」(エッセー32回)のケース。わが家で定期購読している英国のEconomist誌(週刊誌)の書評欄とLondon Review of Books(隔週刊書評誌)と米国のNew York Review of Books(隔週刊書評誌)が信頼できる本を選ぶ頼りにしているソースです。3誌とも質の高い雑誌ですから、厳選された本を書評しています(ときに、有名なライターの本でも容赦なく批評)。London Review of Booksと New York Review of Booksは書評専門誌ですから、内容が充実しています。評者(書評の対象となるテーマに詳しく、ほとんどの場合、その分野についての著作がある学者やライター)が、内容を詳しく紹介しながら読ませる文章で評価をしています。
その長さは1頁から4頁くらいで読み応えがあります(4頁だと20分はかかるので、相当な長さ)。長い記事の場合、しばしば、同テーマについての著作数冊を同時書評という手法がとられています。「原爆事故 ニアミスの恐怖」の元になったEric Schlosserの著作“Command and Control:Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety”は、3誌がいずれも取り上げていたので、これは重要な本だと思い紹介しました。これら英米の2書評誌は、単なる本の紹介ではなく面白い読み物ですので、手にとるのが楽しみです。日本では書評を扱うのは、新聞と雑誌の書評欄ですが、短いですね。長くて新聞は半頁、雑誌は1頁でしょうか。日本と英米の書評文化の違いを感じます。
「ノルマンディ上陸作戦の舞台裏」をテーマにとり上げるきっかけは、町の書店でみつけた写真週刊誌Paris Matchと歴史専門月刊誌Histoireが共同編集した“あの1944年の素晴らしい夏”というタイトルの雑誌でした。ノルマンディ上陸から8月下旬のパリ解放
にいたるまでのヒストリーを伝えるもので、当時起こったことの全体像が鮮明にわかる内容でした。筆者は仏米英の歴史家やレジスタンスの戦士です。ぼくはこの雑誌に大いに啓発されました。それにしても、フランス人は歴史好きですね。ことあるごとに、雑誌は特集を組みます。今年は、第一次世界大戦開戦100周年、ノルマンディ上陸70周年の年ですから、書店には何十種類の本と雑誌の特集が並んでいます。
Antony Beevorの”D-day Battle for Normandy“は、インターネットで「ノルマンディ作戦に関する最良の本」で検索して見つけたものです。何冊かあるなか、彼の評判を知っていたこと、刊行が2009年で最新の資料を利用していること、書評で称賛されていることを確認し、最終的にアマゾンで序章を試し読みして面白いと思い入手しました。期待通り膨大な資料を駆使してリアリズムで史上最大の作戦を再現し、最前線の兵士の体験と連合軍の空爆の犠牲になったフランス市民の体験が描かれている優れた本でした。
ノルマンディ上陸70周年はヨーロッパでは一大イベントですから、フランスのTV、BBC、ARTE(仏独共同TV局)が特集ドキュメンタリーを放映していたのでいろいろ見ましたが、YOUTUBEにもずいぶんお世話になりました。半世紀ぶりの映画「史上最大の作戦」、BBCのダブル・エージェントに関するドキュメンタリー、スペインTV局のガルボ・インタビューなど大いに参考になりました。ぼくのような田舎で暮らす者には、ありがたい文明の利器です。
エッセーの核になったガルボのことを知ったのは、“D-Day”のなかで彼のことが書かれていたからです。数パラグラフでしたが、これは面白いと思い、直ちにインタネット・リサーチにかかり、調べれば調べるほど面白く、MI5のこの二重スパイ作戦について書かれた本数冊のなかから”Double Cross”を選びました。決め手になったのはAntony Beevorの書評とYOUTUBEで見た著者Ben Macintyreのこの本に関するTVインタビューです。この著者はプロだと直感しました。
以上が「ノルマンディ作戦の舞台裏」の舞台裏です。信頼する本を見つけるための極意はありませんが、ぼくの場合、いろいろ読んで試行錯誤をしながら、最後は自分のカンでこの本はいい、この著者は信頼できると判断をしています。
梅本さんは新聞ウオッチのベテランですが、記事の信頼度を測る基準あります?
土野繁樹
公開対話(7) 2014.06.25
NHKの朝の連続テレビ小説(朝ドラ)『花子とアン』は、「赤毛のアン」の翻訳者・村岡花子の明治・大正・昭和にわたる、波乱万丈の半生記で、朝時間があるときに時々見ていますが、結構面白いです。実在の人物たちのドラマが興味をひきます。土野さんが2時間かけて、「薔薇と水仙の周りの草むしり」をされたことを知り、なぜか朝ドラを想起しました。古典的な西洋の香りがしたからでしょうか。「赤毛のアン」はカナダの話ですが…。
そういえば、主人公の村岡花子は、英語が大好きで、プレゼントされた大判の英語辞典を使いながら出版社で初の翻訳の仕事をはじめます。マーク・トウェインの『王子と乞食』です。日本には洗練された翻訳文化があることを公開対話(5)で少し触れましたが、それは、村岡花子のような先達たちが営々と積み上げてきた努力の結晶だと、ドラマを見ながら思いました。誰に強制されるわけでもなく、偶然が重なり、周囲の支援を得て、自分が一番わくわくする天職に導かれていくさまは、見ていてこちらもわくわくしてきます。
土野さんの公開対話(6)を拝読して、日本が「翻訳文化」であるとすれば、フランスなど欧米は「批評文化」が発展しているのだろうと感じました。読むに値する(聞くに値する)批評は、成熟した大人の行為だと思います。批評対象を正確に客観的に理解し、分析する知識と知的能力がまず必要でしょう。さらに、批評対象と対等に渡り合い、その本質に鋭く切り込むには、批評者に応分の知性と経験と洞察力が求められるのだと思います。さらに、称賛するにせよ、批判するにせよ、そこには批評対象に対する深い尊敬と、愛情(敬愛)がなければならないと思います。要するに、プロ同士が正々堂々と知のバトルをしている。そんなイメージです。
翻って、翻訳文化の日本は、知の対象は河の上流から下流に自然に流れてくるものであり、対等に対峙し、リスペクトを込めて渡り合うものにはなりにくいのかもしれません。長く中国大陸から文化・文明と、政治、経済、社会の諸制度を移入し、明治維新後は、西洋先進諸国から同様のことをしてきた日本は、批評が苦手なのかもしれません。知的資産を一方的に移入する場合、等身大の自分を冷静に客観視する必要がないからです。自立した個を確立する文化が批評の基盤を生む。自立した個同士だけが、互いを正確にフェアに評価しあえる。一方的に言い募るのでなく、感情に任せて相手を攻撃するのでもなく、知のキャッチボールとしての対話ができるかどうか。どうもここがポイントのような気がします。
というようなことを考えていると、日本の新聞などの書評欄が土野さんの説明された欧米メディアに比べ、極端に簡略で内容が浅いものになっている理由も少しわかる気がします。とはいえ、この2年ほど、新聞6紙(読売、朝日、毎日、日経、産経、東京)を読み比べる仕事を試みててきた中で、私自身は、書評が載る日曜日の新聞が一番好きです。どんな本が選択され、どんな書評がされているかは、純粋に知的な興味を引き立てるものです。上質な批評は、香り豊かなコーヒーのようで、実に魅力的ですね。
日本の翻訳文化は、素晴らしい資産だと思っています。同時に、それが私たちのメンタリティーにある偏りをもたらしていることも自覚しないといけないのだろうと感じています。翻訳文化と批評文化をつなげ、新しい日本の知的地平を切り開くことはできないものか。そんな問題意識を土野さんとの対話を通して得ることができました。日本の最近の流行語に「マイルド・ヤンキー」や「反知性主義」があります。土野さんは、フランスからご覧になって、日本の最近の状況はどのように見えておりますでしょうか。
「知能」とは、「答えの有る問い」に対して、早く正しい答えを見出す能力。
「知性」とは、「答えの無い問い」に対して、その問いを、問い続ける能力。
含蓄のある指摘です。
梅本龍夫
公開対話(8) 2014.06.30

村松花子の「花子とアン」面白そうですね。朝ドラとは無縁になったので残念です。
日本は世界でもまれなダイナミックな雑種文化で、ご指摘のように翻訳がはたした役割は大きいと思います。
日本の翻訳文化について、ぼくも思うところいろいろあります。というのも、編集者としてブリタニカ国際大百科事典の刊行(翻訳70%、書き下ろし30%)のプロジェクトに参画し10年、ニューズウィーク日本語版の編集を8年、その他単行本の翻訳出版もやりましたので、翻訳文化のおかげで日々の糧を得ていたようなものです。以下、徒然なるままに、わが翻訳論です。
昔、ドナルド・キーンさんが、神田の古本街に行けば世界のあらゆる文学作品の翻訳本がある、ニューヨークの比ではない、とどこかで書いていました。それは、日本人が知的にハングリーであった時代のことで、いまでは外国文学の作品は売れないとの理由で、点数も販売部数も激減しているのではないでしょうか。ミステリーは別ですが。
ニューズウィーク日本版は、翻訳の質が勝負の雑誌でした。英語の記事を早く正確に訳しかつ読ませる日本語にするため、たしか5工程を経て、最終稿にしていました。その工程のなかに、バイリンガルの米国人のチェッカーがいて、厳しい関門を設けていました。英語のニュアンスを本当に伝えるためには、これぐらいの努力がいりますね。
ぼくも翻訳をやりますが、いい翻訳ができる人は、英語力、内容の理解力、日本語力が同等にあると思います。原作が面白くても、訳者に日本語力がないため、魅力のない本になっている例が世のなかには一杯ありますね。これでは、原作者が不幸です。
サイデンステッカーさんが『源氏物語』を英訳し、それが日本翻訳協会賞を受賞したときのことを思いだしました。翻訳協会の会長が「森鴎外の『即興詩人』の翻訳のように原作より良いと言われるのが、最高の翻訳だ」とスピーチしました。それを受けてサイデンさんは「わたしはベストの翻訳は原作に限りなく忠実であるべきだと思う。その作業は贋金つくりに似ている」と応じていました。原作のニュアンスを伝えるために悪戦苦闘した人の言葉だと思います。
内容のある外国語の翻訳版(本と記事)は、読者にとって、新しいアイデアと視点に巡り会える機会ですね。なるほど、こんな視点でものが見られるのか、という新鮮な発見の手段だと思います。視野が広がりますね。
米国は翻訳書があまり刊行されない国ですが、フランスの経済学者ピケティの『21世紀の資本』の英訳版が3月に刊行されると、すぐベストセラーになり話題になっています。ある書評は「フランス語で読むのと同じ愉しみがある」とその英訳を称えていました。30カ国の出版社が翻訳権を買ったとのことですが、日本語版はみすず書房が獲得しました。この大著の出版を決意したみすず書房に敬意を表しますが、残念ながら刊行は2017年とのことで、日本の読者はそれまでお預けです。これでは、本のテーマである「不平等の拡大」をどうするかについての国際的対話に参加するタイミングを失いますね。この本はチームを組んで6か月くらいで刊行すべきでしょう。
流行は世相の波頭といいますが、ソフト・ヤンキーと反知性主義も世相の反映でしょう。これが流行語になっていること知らなかったので語る資格はないのですが、以下、ぼくの印象です。前者は、卒直に言って“こりゃなんじゃ”です。米国人が作った言葉ならユーモアありますが、それを電通の人が無理やり流行らしたような言葉ですね。後者はネット右翼やNHK会長などの発言へのリアクションかなと思うと理解できますが、コンテクストがわかりません。ともあれ、日本が時代遅れのナショナリズムに煽られて、反知性主義の時代へ入っているのは確かです。
梅本さんが、影響を受けた翻訳書はなんでしょう?
土野繁樹
感想をお待ちしております。
アーカイブ