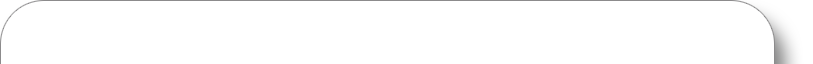土野繁樹
最後の紙版の表紙
米国メイン州のコルビー大学の留学生時代、ひと夏ニューヨークで暮らしたことがある。ベトナム反戦デモでアメリカが荒れていた1967年のことである。マジソン街のビルの最上階にあるNewsweekのロゴ(写真)を見たのはその頃だった。夜になると摩天楼の一角にネオンのロゴが照らしだされ、その存在を誇示していた。
その夏、ジャーナリスト志望だったわたしは、ニューヨークの読売支局で見習いの仕事をした。当時の支局長・牧野拓司さんにお願いしての押しかけ研修だったので無給だったが、現場の体験は面白かった。その頃、ニューヨーク=東京間の特派員の通信手段はテレックスで、支局ではAPのティッカ―の音が絶え間なくしていた。コンピュータはまだ黎明期で、全世界で3万6000台しかなかった時代である。
予期せぬことが起こるので、人生は面白い。その夏から20年後、わたしはNewsweek日本版の編集長として、Newsweek本社ビルにある‘週のトップ’(Top of the Week)と名付けられた特別食堂に、スミス総編集長、オーケンクロス国際版編集長の午餐ゲストとして招かれていた。食堂の上の階にはNewsweekのロゴが鎮座していたのである。
あの日から時は流れて25年。2012年12月31日をもって、ほぼ80年続いたアメリカを代表する週刊誌Newsweekの紙版は姿を消すことになった。最終版の表紙(上の写真)のタイトルは‘#lastprintissue‘(最後の紙版)とある。#はツイッターの象徴ハッシュタグだ。同誌は元旦から完全にオンライン版に移行した。
TBSブリタニカ 1998年刊
1986年にわたしがNewsweek日本版に参画しておどろいたのは、本誌の巨大な‘編集マシーン’の存在だった。毎週一冊の雑誌を刊行するために、ニューヨーク本社の取材・編集スタッフ380人、海外特派員80人、米国内支局10、海外支局14があり、編集長の号令一下最新のニュースが報道・分析(とくにカバーストーリー)されるという大規模なオペレーションだった。
当時、NewsweekとWashington Postの社主だったキャサリン・グラハム女史は、ウォ-タ-ゲ-ト事件報道でニクソン大統領を辞任に追い込んで以来、アメリカで最も影響力のある女性と呼ばれていた。わたしは、たまたま彼女が出席した次週のラインアップを決める編集会議に出たことがある。
会議が一段落したあと、スミス編集長が言った。「さきほどケイ(キャサリンの愛称)からヘンリー・キッシンジャーと会った話を聞いた。面白いので、ご本人から紹介してもらいましょう」。グラハム女史は「昨日、ヘンリーが最近はじめてゴルバチョフに会った印象を‘歴代のソ連の指導者とはまったく違う男だ’と興奮気味に言っていたわ」と言い少し説明した。そのあとゴルバチョフについて短時間の質疑応答があった。
数日後、東京に戻ってきて次週の記事リストを見ると、カバー・ストーリー(表紙になるトップ・ストーリー)はゴルバチョフになっていた。あの会議のあと、編集長はゴルバチョフを表紙にする決定をし、その時点でNewsweekの巨大な編集マシーンが始動したわけだ。この体験でわたしは、優雅で美しいグラハム女史のパワーを垣間見ることができた。
グラハム女史の自伝に『わが人生』がある。この本は裕福な家庭(父親はWashington Post社のオーナー)に育ったひとりの女性の波瀾万丈の物語だ。Newsweek社長だった夫フィリップ・グラハムの自殺で、彼女の人生は逆転する。そのとき彼女は46歳、4人の子供を育てる家庭の主婦であった。この自伝のハイライトは、一夜にして大メディアのトップになった彼女が、男社会の壁に阻まれ時に涙を流しながら孤軍奮闘する章だ。実に正直に書かれているので読者は感動する。
わたしはこの本の日本語版の編集を担当し、プロモーションのために来日した彼女を数日お世話したことがある。帰国したグラハム女史から予期せぬ手書きの礼状が届いた。誠実で律儀だった彼女は10年前に亡くなった。
1989年11月20号の表紙
わたしが日本版編集長をやっていた頃、昭和天皇の逝去、天安門事件、ベルリンの壁崩壊、ソ連邦崩壊、湾岸戦争など世界的ニュースが次々と飛び込んできた。とくにベルリンの壁とソ連の崩壊による東西冷戦の終結は100年に一度の歴史的大事件だったので、ベルリンやモスクワ特派員のファックス原稿を興奮して読んだものだ。この時ほど‘ジャーナリストは歴史のファースト・ドラフト(初稿)の書き手’という言葉を実感したことはない。
80年代のNewsweekは最高潮で部数380万(日本版など海外版も含め)を達成し、広告収入も大きかった。‘最後の紙版’に古き良き時代を象徴するような記者の回想がいくつか載っている。たとえば、海外特派員の取材費や交際費がいかに潤沢であったかを、スター記者だったド・ボーチグレーヴが次のように語っている。「どこへ行くにも飛行機はフアースト・クラス、ホテルは五つ星。あるとき、インドで崖崩れに出会い、道を開いてジープを動かすために300人のシェルパを雇ったこともある。30年間在職したが、一度も経費のことで文句を言われたことはないよ」。
ユーモア誌Madのオンライン版の表紙になったティナ・ブラウン
しかし、インターネットが普及しはじめると、週刊誌の黄金時代も終わり、しだいに部数は減っていった。2000年の段階で314万だった部数が2012年には150万と半減し、広告収入も激減し年間赤字が4000万ドルまで膨らんだ。
現在、アメリカ人の39%がニュースはオンライン版で読み(Pew世論調査)、オンライン版の広告売上が紙媒体のそれを超える(昨年逆転して373億ドルvs343億ドル:eMarketer調査)という時代の流れに、Newsweekは抗しきれず紙版からの撤退となった。
今回の決定の2年前すでに、この雑誌の所有権は半世紀続いたWashington Post 社からオーディオ機器メーカーのオーナーに移っていた。その売値は1ドル!経営悪化で身売りの噂はNewsweek社内で広まっていたが、売値が1ドルと知った編集スタッフの多くが「笑うべきか、泣くべきか」わからない複雑な気持ちだったという。
新しいオーナーのシドニー・ハーマンは、米国雑誌界の寵児で、人気オンライン・ニュース雑誌・The Daily Beastの編集長ティナ・ブラウン女史に編集長就任を要請する。英国生まれの彼女はVanity FairやNew Yorker の編集長を歴任し、その手腕には定評がある。しかし、彼女の紙版維持のための2年間の努力も実らなかった。しかし、彼女はオンライン版Newsweek Globalを2月に立ち上げることを宣言している。その意気やよしである。
しかし、Newsweek元東京支局長で友人のトレシー・ダルビー(テキサス大学ジャーナリズム科教授)は「ティナ・ブラウンの雑誌を救うための果敢な試みに敬意を表する。しかし、すでにあるNew York Timesなどのオンライン版との棲み分けをどうするのかが問題だ。前途多難だと思う」と言う。
これがおそらく大方の予測だろう。しかし、インターネット時代のジャーナリズムのモデルはまだ確定していない。ひとつだけ確実なことは、新聞や雑誌の主流はいずれオンライン版になるということだ。タブレットの急速な普及でそれはますます加速している。
オンライン版メディアの最前線アメリカでいま起こっていることは、いずれ日本でも起こるだろう。現在、日本の新聞や雑誌は、欧米のクオリティ・ペーパーのオンライン版に比べて見劣りがする。たとえば、日本の主要紙とNew York Timesのそれを比べると天と地の差がある。New York Timesのオンライン版はいまでもトップレベルなのだが、昨秋BBC前会長のマーク・トンプソンを本社の社長兼CEOに迎え入れた。BBC放送のノーハウを取り入れ、来るべき全面的なオンライン版新聞に備えるためだ。日本のメディアはオンライン版に力をいれるべきだと思う。
Newsweek は紙版に別れを告げ、デジタル版に移行した。これは、わたしのように活字で育った人間には残念な思いもあるが、時代は変わったのだ。ブラウン女史は‘最後の紙版’の編集長メッセージ‘新しい章’で「ときに、変化は良いことではない。しかし、それは必要なことだ」と言っている。そして彼女はNewsweek Globalに果敢に挑戦する。
Good Luck, Tina Brown!
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】