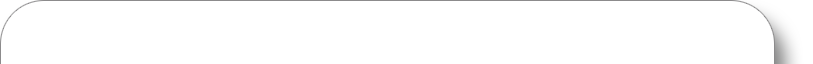【リグミの解説】
無人探査機の開発
「ソフトパワー」の競争は、コンテンツを創る国とコンテンツを消費する国が、互恵の関係になれます。相互依存の好循環を作り、「Win-Win」の関係を構築できる可能性が常にあります。一方の「ハードパワー」競争の一番右側にある軍備増強はどうでしょうか。
本日の読売新聞の1面トップは、防衛省が「北朝鮮、中国の脅威を睨み、無人探査機を開発」という記事です。今年4月に北朝鮮が発射失敗し、低い高度で落下した弾道ミサイルも探知できなかった問題などを踏まえ、現有システムの穴を埋める探査システムとなります。今回の対応の理由として、北朝鮮の弾道ミサイルの脅威もありますが、むしろ中国との衝突のリスクを想定してのものと思われます。
「ハードパワー」の競争
「ハードパワー」を求める軍拡競争の問題は、常に「Win-Lose」を想定したものだということです。競争を仕掛ける側は、一瞬優位に立ちますが、仕掛けられた側は脅威を感じ、ほぼ確実に対抗策を取ろうとします。結果、軍拡はいたちごっこになり、一触即発のリスクを高めています。冷戦時代の軍拡は、ついに地球を何度も破壊できるレベルまで核兵器を積み上げる愚行につながりました。
核は一度使えば、結果は「Lose-Lose」しかありえない、という冷徹な現実に直面した米国と旧ソ連が、かろうじて均衡を保つことで世界は破滅せずに済みました。1962年、ソ連によるキューバへの核ミサイル配備で、第3次世界大戦の危機が一気に高まりました。2008年に出版された『One Minute to Midnight』という本によると、悪夢が現実化する可能性は、一般に知られる以上に高く、文字通り危機一髪であったそうです。
日中の「ハードパワー」比較
ここで少しデータを見てみます。日本と中国は、現在GNPでだいたい「1対1」ですが、人口で「1対10」、国土では「1対25」です。これに対応する両国の陸上兵力の比較は、「自衛隊15.7万人」対「人民解放軍160万人」と「1対10」です。
ところが、領海と排他的経済水域(EEZ)を併せた海洋領土では日本は世界で6番目の広さがあり、15番目の中国のおよそ5倍あります(参照:Wikipedia)。この海上で、しかし中国軍は、駆逐艦数は1.7倍、潜水艦で3倍、戦闘機の数は2倍でと、すべて自衛隊を上回っています(参照:朝日新聞10月28日付朝刊10面)。
この状況に対して、月刊誌「ファクタ」の2012年11月号に米海軍大学のジェームズ・R・ホームズ准教授が寄稿しています。ナポレオン戦争時代の戦争論の本を題材に、「中国政府の費用対効果の分析を見直させることで、東シナ海における中国の冒険主義を阻止できる可能性がある」とし、自衛隊が軍備増強をし、尖閣諸島に移動式ミサイルを配備することまで提唱しています。
しかし、素人が読んでも、この論考が空想的であることはわかります。尖閣に石原慎太郎氏が提唱する船着き場を作ろうとしただけで、日中関係はさらに手の付けられない状況になるでしょう。軍備増強が、いついかなるときも不要かつ無益だとは言いません。キューバ危機後も冷戦が長く続き、軍拡競争が続いた歴史を見れば、「Lose」にならないために、ある種のチキンレースを続けざるを得ない状況をリアリスティックに判断すべきときもあるでしょう。
「ソフトパワー」競争が未来を創る
百歩譲って、日本にとってしばらくは「ハードパワー」の拡充が不可避であったと仮にしても、それは「ソフトパワー」の拡充とセットのものでなければなりません。外交は、机の上で握手をして、机の下で蹴り合う交渉だと言われますが、がっちり握手したくなる「ソフトパワー」を置き去りにして蹴り合えば、東アジア全体が「Lose-Lose」の負の螺旋に巻き込まれていきます。
無人探査機が完成し、導入されるのは、2020年想定です。この間に、日中の「ソフトパワー」競争が健全に発展し、軍備拡張のチキンレースは無益だと双方の政治家と国民が気付くことを願います。
(文責:梅本龍夫)
讀賣新聞
【記事要約】 「無人探査機、開発へ」
- 防衛省は、「対空型無人機システム」の開発に着手する方針を固めた。同システムは、国産の無人探査機で、弾道ミサイル発射を早期に探知できる高感度の赤外線センサーを備える。北朝鮮の弾道ミサイルや、軍事力を増強する中国の動向に対して、警戒監視能力の一層の向上が必要との判断による。
- 防衛省の現在の弾道ミサイル探知システムは、地上配備型のレーダーとイージス艦となる。米軍の早期警戒衛星(SEW)の情報提供も得ている。ただ、レーダーなどは、弾道ミサイルが一定の高度に上がった段階でないと探知できないという制約がある。今年4月に北朝鮮が発射失敗し、低い高度で落下した弾道ミサイルも探知できなかった。
- 実用化を目指す無人探査機は、高度約1万5000メートルを飛ぶため、低い高度の動きを探知できる。パイロットが乗らないため、22時間ほどの連続航行も可能となる。防衛省は、4年間で計30億円の予算を計上。無人機の試験機の基礎設計を行い、試験機完成後に強度調査を進め、2020年度の実用化を目指す。
(YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/)
朝日新聞
【記事要約】 「盛り土造成地、進まぬ分布調査」
- 国は、2006年の宅地造成規制法改正に伴い、148自治体に対して盛り土造成地の分布状況を調べ、地震で崩れる危険性のある盛り土については、対策を講じるよう求めている。しかし、114自治体が、調査未着手のままだ。都市部のリスクの実態把握が遅れている。
- 調査未着手の自治体の主な理由は、以下の通り。▽「予算を要求したがつかなかった」(京都府)、▽「予算は住宅の耐震化を優先させた」(福岡市)、▽「液状化の対策に人手を取られている」(千葉市)―。
- 残り34自治体のうち、16自治体は調査中。調査を終えた18自治体のうち9自治体(宮城県、東京都、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、静岡市、堺市、広島市)は、「住民の不安をあおる」「対策工事に関する国の方針が見えない」などの理由で、公表していない。一方、2007年に公表した川崎市は、「市内に造成地が多く、住民の安全確保のために必要と考えた」と話す。
(朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/)
毎日新聞
【記事要約】 「東電、福島に復興本社」
- 東京電力は、「福島復興本社」(仮称)を来年1月にも福島県に設置する方針を固めた。全社員の1割強にあたる4千人以上が配置され、福島第1原発事故の被災者賠償や除染体制を拡充し、復興支援を一体的に進める。
- 復興本社のトップは、副社長級とし、現地の常駐させる。除染担当を3倍の300人規模にし、放射線量の引き下げを急ぐ。地元の雇用創出と電力供給の確保の両面から、浜通り地区で高効率の石炭火力の増設を検討する。約3万8000人の全社員が福島で支援業務に携わる。年2~3回福島入りし、年間延べ10万人体制で家財搬出など生活支援にあたる。
- 東電首脳は、「福島が新生東電の原点であることを示したい」と話す。そのために、全社員が現場に接することで、事故の教訓を全社で共有できるようにする。賠償支払いの判断の権限などを本店からすべて復興本社に移行し、復興業務に当たる人員も現行の3500人から4000人に増強し、信頼回復につなげる狙いだ。
(毎日jp http://mainichi.jp/)
日経新聞
【記事要約】 「電力事業、アジア開拓」
- 東京電力福島第1原発事故で原発輸出に逆風が吹く中、商社や重電メーカーは相次いで火力などを電源とする電力供給システムの輸出に乗り出す。経済産業省などが支援をする。電力不安を抱えるアジアが有望市場だ。
- 三菱商事と三菱重工業は、インドで高効率ガス火力発電事業に参入する方針。東芝は、インド全土の送配電システムの輸出に向けた調査を始める。日立製作所は、大型蓄電池や電圧変動の制御装置のインドへの輸出を狙う。日本総研・東芝・日本IBM・清水建設は、マレーシアの官庁街のビルエネルギー管理システムを導入する。Jパワーと中国電力は、カンボジアで石炭火力発電所建設に向けた調査を始めた。
- 経済成長するアジア新興国は、電力不安を抱えており、2035年までに電力需要は2.5倍に拡大、発電・送配電への投資は合計で8.8兆ドル(約700兆円)に達するという予測もある(日本エネルギー経済研究所の試算)。中国リスクを踏まえ、日本企業によるインドや東南アジアへの生産拠点の移転が増えると見られる。電力不安の解消は、日本企業の進出を支えることにもなる。
(日経Web刊 http://www.nikkei.com/)
東京新聞
【記事要約】 「3割、避難先メド立たず」
- 「原子力災害対策重点区域」が原発から半径30キロ圏に拡充されたことに伴い、新たに区域に入る20道府県83市町村(福島県を除く)のうち、3割超の29自治体で避難先確保の見通しが立っていないことが判明した。安定ヨウ素剤の住民への配布方法も、9割が対応を決めていない。共同通信のアンケートによる。
- 83自治体の対応は、以下の通り。▽「避難先を確保」=12自治体(14%)、▽「確保していないができる見通し」=28自治体(34%)、▽「確保したが不十分」=10自治体(12%)、▽「見通しが立っていない」=29自治体(35%)、▽無回答=4自治体(5%)―。
- 原子力災害対策重点区域は、原発事故に備えて事前に対策を取る地域。放射線量を測定するモニタリングポストを設置するとともに、事故や避難に関する情報を住民に確実に伝えるための防災無線などを整備する。原子力規制委員会が10月末に決定した原子力災害対策指針で30キロ圏に拡大されたことで、自治体の防災計画づくりが難航することは必至だ。
(TOKYO Web http://www.tokyo-np.co.jp/)
【本日の新聞1面トップ記事】アーカイブ