わたしは10年前から、ひょんなことからパリから南500キロのところにあるドルドーニュ県の小さな村で、一年の大半を妻と二人で暮らしている。ドルドーニュは、珍味フォアブラの産地、クロマニヨン人の描いたラスコー洞窟画、1000の城で知られている。わが家の周りはまったくの田園地帯で、数軒隣家があるだけだ。1キロ近く歩くと、中世の風情を色濃く残す人口300人の村サン・ジャン・ドコールがある。そこには11世紀の教会と15世紀の城が建っている。教会の鐘の音が時を告げ、村役場の三色旗がたなびく生活空間のなかでの暮らしは快適だ。

わたしはフランスとは縁のない男だった。いわば純粋英米派であった。というのも、英国で誕生したブリタニカ百科事典、米国の週刊誌ニューズウィーク日本版の編集をしていたからだ。30年間、仕事を通じてアングロ・サクソン文明の視点で世界を見てきたのだが、当地の田舎暮らしでフランス文明の視点が加わった。そのおかげで、世界を見る目が微妙に変わったと思う。
筆者 村の花祭りの準備
フランス語は、こちらで暮らしはじめる前に、横浜日仏学院の週3時間のコースに半年通っただけで、まつたくのゼロ(雑誌Elleのタイトルがなにを意味するか知らなかった)からの出発であった。奥方はフランス語ができるので、日常生活に支障はなかったが、当初、わたしの村人との交流はBonjour(ボンジュール)一本槍だった。今ではルモンド紙が読めるようになり、テレビ・ラジオのニュースがほぼ分かるようになった。しかし、まだレベルの高い会話はできない。
都会育ちのわたしにとって、田舎暮らしそのものが初体験だった上に、選んだ場所がフランスの奥深い田舎だったので、そのインパクトは新鮮かつ強烈だった。この村での暮らしと東京時代とを比べて、なにが一番違うかと言えば、時間についての感覚だろう。ここでは、とにかく時間がゆっくり流れるのである。
.jpg)
丘の上のわが家
わが家は、1827年に建った石造り240㎡の平屋である。建築様式は17世紀から19世紀前半に流行したシャルトルーズと呼ばれるもので、昔は地方のブルジョワや地主の住居や別荘であったようだ。壁は70㎝もあるから頑丈で真夏でもクーラーはいらない。食堂の暖炉には建築時のままの鶏や豚を丸焼きにする装置があり、いまでも利用できる。歳月を経て屋根の赤瓦は薄茶色となり、壁は淡い灰色に変色し、玄関の入り口にある石垣には苔がむしている。ここで暮らしていると、百年前、二百年前、いや千年前もそれほど昔とは思えない。
村の広場に立って、ロマネスク様式の円いドームの教会、二つの尖塔がある城を眺めていると、中世世界にタイムトラベルをしている気分になる。教会はフランス革命時には荒れ果て、干し草の倉庫になっていたという。現在の城主ド・ブモンさんは貴族の末裔で16代目、37年間、村長でもあった。教会に隣接して大きな屋根で覆われたオープンスペースがあるが、ここは昔のマーケットだ。いまでも夏祭りのダンスや教会コンサートあとのパーティの会場として使われている。広場の中心には、20世紀二つの大戦で戦死した村出身の兵士21名の名前が刻まれた慰霊碑がある。眼前に歴史がある。日常生活のなかに過去が生きている。
.jpg)
ラスコーの洞窟画
わが家から車で20分のところに、クロマニヨン人が暮らしたヴィラ―の丘がある、その丘の下には鍾乳洞があり1万7千年前に描かれた洞窟画がある。ラスコーの壁画に比べると、画の数はすくないが、夏になると観光客が訪れる。ここの人を襲う野牛や青い馬を見ていると、現代人の祖先クロマニヨン人を身近に感じるのである。
クロマニヨン人と言えば、横浜に住んでいたころの奥方と交わした会話を思い出す。ある日、彼女はフランスの雑誌の不動産広告を見ながら「このドルドーニュの家、素晴らしいわね」と弾んだ声で言った。わたしは「いいね」と答えたものの、彼女がまさか本気だとは思わなかった。翌日からヤードは、その地がいかに面白いところかを語りはじめた。ワインが美味しく、風光明媚で、英仏百年戦争の地で・・と説得にかかったのである。「フランス語ができないから、無理だよ」と言うわたしに、彼女は「勉強すればできるわよ。それにドルドーニュは人類がはじめて文明化し芸術に目覚めた土地なのよ。ラスコーの洞窟画のこと知ってるでしょう」と言ったものだ。心機一転、まったく新しいことをやりたかったわたしに、この一言は効き目があった。わたしは文明と芸術と言う言葉に弱い。

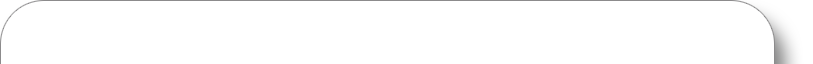
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
