「事故は起きるもの」
自動車ジャーナリストの清水和夫さんが、自動車月刊誌『カーグラフィック』で連載している「WARNING LAMP」で、関越道バス事故を取り上げています(2012年7月号)。
マスコミは、おしなべて長距離バス運転の過酷な労働条件が事故の原因になったとの論調ですが、清水さんは違う見方をしています。運転手の状態は、事故の直接の原因にはなったかもしれませんが、あそこまで悲惨な事故になった理由は他にある、というのです。
1.道路構造
最初に道路構造について問題提起をします。ドイツやアメリカの道路は、加害性を十分に考慮して設計されていますが、日本はどうなのでしょうか。
事故現場に赴いた清水さんは、橋の欄干にガードレールをオーバーラップさせるように求めた1998年以降の道路構造になっていなかったことを発見し、これが被害拡大の張本人であったと断じています。
2.シートベルト装着率
つぎに、シートベルト装着率に着目します。最前列に座っていた人がシートベルトをしていて助かっており、席ごとの状況をきちんと分析すれば、シートベルトの装着率が低かったことも事故被害の拡大につながったことがわかる、と推察しています。
3.居眠り防止システム
居眠り運転をしていても事故を未然に防ぐ取り組みもあります。車線逸脱防止を目的とした「ギザギザ付きの白線」でドライバーに警告することも一案。車載カメラで白線を読み取る車線逸脱警報/車線維持機能もバスの安全性には欠かせない機能となります。
4.ドライブレコーダー
バスにはドライブレコーダーを設置して、日頃から安全運転の要となる「ヒヤリ&ハット」を監視することも有効な手段となる、と清水さん。
「過酷なバス運行の労働条件」や「運賃の低価格化」がもたらした事故、という側面は確かにあると思います。しかし、「事故は起きるもの」としてリスクを低減する道路構造の研究と普及、バス側の技術やシステムの導入を促進すべき、という清水さんの意見は重要で、既存の報道への「セカンドビュー」としても傾聴に値します。
原発事故は「人災」
「事故は起きるもの」は、原発もまったく同じであることがわかりました。さらに原発の場合、一旦事故が起きれば、その影響は甚大であり、被害状況は収拾不可能とすら言えます。科学的な事故原因検証こそ、すべての出発点になります。政府も東京電力も専門家もマスコミも、そして私たち一人一人も、同じ場所に立ち戻るべきだと思います。
7月5日には、東京電力福島第1原子力発電所事故に対する国会事故調査委員会の報告書が発表されました(参照:
国会事故調)。地震・津波への対策を取る機会は何度もあったのに、意図的に先送りしてきた「人災」であると断じたことは、多くの人々の疑問に明確な答えを示したものとして高く評価できます。
原発に対する新たな規制強化の動きがあるたびに、東電は電気事業連合会を通して反対の圧力をかけてきました。規制強化されると原発の稼働率が下がり利益が圧迫されることと、これまで展開してきた安全性の主張を続けられなくなり、訴訟で不利になるおそれがあるため、と報告書は分析しています。原子力保安院が情報や専門性で東電に劣ることもあり、東電の「虜」になっていった、という問題指摘も重要です。
電力会社の「構え」
原子力エネルギーを考える上で、2つの重要な前提があると思います。1つは、「一旦原発事故が起きれば、その被害は甚大であり、最悪コントロール不可になる」ことです。もう1つは、「人間はかならずミスを犯す」ということです。このことを前提とすれば、対策の基本理念は明確になると思います。
最も必要なのは、常に最悪を想定し、リスク要因に対する不断の探究をつづけ、安全対策の見直しと更新を継続する経営者(原発の運用責任者)の「構え」です。法規制の強化や、独立した規制機関による管理・監督の徹底などは、当然必要です。しかし、「当事者」である電力会社が、原発のリスクの特殊性と人間がミスをするものということを自覚し、痛切な思いで事業運営を預らない限り、重大事故はまた起きます。
国会事故調の報告内容は、政府と東京電力に関するものですが、すべての電力会社に共通する問題指摘であると考えるべきです。再稼働した関西電力大飯原発を含めて、50基の原発すべての安全対策と、運営「当事者」である電力会社の経営実態・運営状況を問う必要があります。
事故原因を徹底追及すれば、責任問題が浮上します。そこで肝心なところは曖昧にし、隠ぺいしようとする力学が働きます。これが日本の権力構造や組織体質の大きな問題点です。電力会社の経営の「構え」とは、原因と結果に対して責任を負うということです。事故の真の原因を徹底究明し、責任の所在を明確にしない限り、国民の不安と不信は払拭できません。そして問題は再発します。
ダルビッシュのアメリカ体験
東京電力の経営陣には、今年メジャーリーグに渡りがんばっているダルビッシュ投手のアメリカ体験が役立つかもしれません。
米国では交通事故を起こしても謝らないのが鉄則と言われます。うっかり謝ってしまうと保険会社の調査や裁判で不利になるからだ、という解釈です。ここには「原因責任」と「結果責任」の問題が隠されているように思います。
ダルビッシュは、「結果責任」を意識して謝ったのでしょう。しかし、アメリカでは、良いピッチングをするためにきちんと準備をし試合に臨んだのであれば、結果は結果であり、責任は問われません。次で取り返せば良いからです。しかし、謝るということは、きちんと準備をしていなかったと認めることになると解釈されます。謝るということは、「原因責任」があることを認めることになります。そうなるとメディアが黙っていず、ダルビッシュ叩きを始めることになります。そこで監督は発言に気をつけるように忠告をしたのです。
アメリカは「原因責任」の国。日本は「結果責任」の国。
ダルビッシュがアメリカで体験した文化の違いとは、このことだったのだと思います。
「原因責任」がカギ
ここに「日本問題」があります。
「原因責任」が考え方の基本にあれば、事故の発生原因を根本のところまで徹底して追求します。また事故原因を1点に絞ることなく、多様な要因を洗い出し、総合的に追求することになります。その上で責任を負うべき人や機関がきちんと責任を負うことになりますから、大変ではありますが、その分教訓も深いので、自ずと再発防止策も徹底して考えられることになります。
しかしこれが「結果責任」を基本とする場合には、原因追求が不徹底かつ甘く、焦点のぼけたものとなります。そして、何が真実かよくわからないまま、起きた事象(結果)をきれいに水に流す“禊(みそぎ)”をして終わり、となります。
典型的な禊(みそぎ)の仕方は、現場に近いミドルクラスの人に原因責任を集約させ、とかげのしっぽ切りをするパターンです。しかし今回の原発事故のように、「結果」が甚大で深刻過ぎると、個人で責任を負う人がいなくなります。悪しき集団主義となり、責任そのものがうやむやになってしまうのです。
では「原因責任」はどこまで対象になるのでしょうか。
東京電力の責任は重いですが、原発推進の「旗振り役」と「監視役」という相反する2役を同時に続けてきた経済産業省の責任も同等に重いものがあります。そして時の与党として原子力エネルギー政策を推進してきた政治家も、当然「原因責任」の追及対象です。さらには、福島第1原発の製造納入元である米GE社も製造物責任を問われる立場です。津波を想定していないアメリカの設計思想のまま、原発を日本にもってきたと言われているからです。
テクノロジーとアメリカの事情に詳しいベンチャーキャピタリストの原丈人氏は、GEを訴えるべきだと示唆し、その効果を次のように語っています。
「アメリカの知人によれば、勝訴の結果、GEが東京電力に支払う金額は、東電が4月時点で見込んでいた事故の賠償総額の2兆5000億円(除染の費用は含まれない)を超えるだろうといっていた。日本政府が保障のために投ずる公的資金(税金)も、そのぶんだけ減ることになる。これがいまアメリカでは常識的な考えなのである」
(月刊誌「VOICE」7月号掲載記事より)
日本が世界に発信できること
誰も、原発事故の「責任」を取ろうとしない日本の現状は、異常です。この現状をどこから変えたらいいのでしょうか。事故原因を総合的かつ徹底して追求するのは不可欠です。でもそれと共に大事なのはビジョンではないかと思います。事故から何を学び、未来をどう創造するか、というビジョンです。
7月23日には、政府による事故調査委員会(畑村洋太郎委員長、東大名誉教授、失敗学の専門家)による最終報告書が発表されます。これで、国会・事故調査委員会、民間事故調、東電の社内調査と合わせて、4つの調査報告書が出そろいます。報告書は、提出して「終わり」ではありません。それは「始まり」に過ぎません。
日本が現在、総力を挙げて「原因責任」を追求すべき基礎情報と考え方の枠組みがここにあります。日本は、世界に対して説明責任を果たし、原子力エネルギー政策に対する根本的な提言をする義務があります。今回の重大事故から本気で学び、根本的な対策を打ち立てることができれば、それは世界共有のアセットとなるのです。


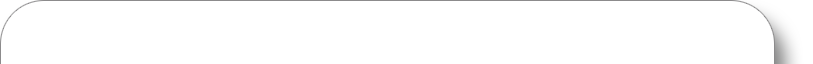
.jpg)
.jpg)
