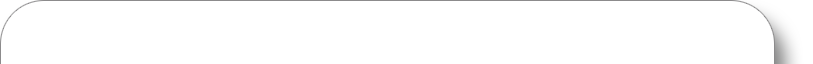土野繁樹
大戦中、最も激しい戦場となったベルギ―のイープル Wikipedia
今から100年前の1914年、新年を迎えたヨーロッパは平和で未来への希望に溢れていた。貿易とテクノロジー(電話、蒸気船、鉄道)が世界を結びつけ、人々はグローバライゼーションの果実を味わっていた。20世紀を代表する経済学者ケインズはその当時のロンドンの暮らしを次のように書いている「朝の紅茶をベッドで飲みながら、世界各地に商品を注文し宅配されるのを待つ」「この状況は、日常的なことで、永続し、ますます便利になるだろう」。これは庶民には高嶺の花のライススタイルだったが、100年前にすでにAmazon .com的世界があったのだ。後世の人々はこの時代を、郷愁を込めてベル・エポック(古き良き時代)と呼んだ。
当時、ベストセラーになった“The Great Illusion”(偉大なる幻想)の著者ノーマン・アンジェル(英国政治家、ジャーナリスト)は、ヨーロッパ経済がこれほど一体化している現状では、戦争は無意味なことである、と書いている。そして、ウィーン、ロンドン、パリなどの大都会の市民の大多数も、英国とドイツが互いに最大の貿易相手国だから戦争など起こるはずはない、と信じていた。
それに、当時のヨーロッパの大国の知識層は文化的アイデンティティを共有していた。彼らはラテン語とギリシャ語を学び、シェークスピア(英)、ダンテ(伊)、ゲーテ(独)、トルストイ(露)、ヴィクトル・ユーゴー(仏)の作品を読んだ。このように彼らは、国籍は違っても思想と知識を共有していたのである。
ところが、1914年6月28日サラエボ(現在、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都)で、オーストリア・ハンガリー帝国(以下、オーストリア帝国)の皇太子フランツ・フェルディナント大公夫妻が、セルビア民族主義に心酔する19歳の学生に暗殺され、それが引き金をとなり、二つの陣営(ドイツ帝国、オーストリア帝国、オットマン帝国vsロシア帝国、フランス共和国、大英帝国)に分かれて4000万の死傷者をだした戦争に突っ込んでいった。
「第一次世界大戦は悲劇であり不要の戦いだった」「避けることが出来た戦争だった」と英国の戦史家ジョン・キーガンはその秀作『第一次世界大戦』(The First World War:1998年)の冒頭に書いている。いまから半世紀前、歴史家バーバラ・タックマンはその名著『8月の砲声』(The Guns of August:1962年 ちくま学芸文庫)で、サラエボの暗殺から開戦にいたる35日間の各国首脳と軍の動きを詳細に調べ、ヨーロッパの悲劇の要因を解明している。
尖閣は21世紀のサラエボになるのではないか、という声がある。現段階では、これは杞憂だろう。しかし、日中間の対立がエスカレートして軍事衝突になる可能性はある。そうなった場合、事態を収拾できるのだろうか。第一次世界大戦は当事国の指導者が誰も望んでいない戦争だった。にもかかわらず、文明を破壊する戦争になった。前記の二人の歴史家は、35日の間、悲劇を食い止めるチャンスは何度もあったと言っている。今回のエッセーでは、そのことを紹介し歴史の教訓にしたい。
100年前のその日の朝、サラエボの空は紺碧だった。前日、軍事演習を視察したフェルディナント皇太子は妃をともなって、知事公邸の歓迎会に向かう車に乗っていた。すると突然、ひとりの若者が皇太子の車にむかって爆弾を投げつけた。幸い、その爆弾は当たらず別の車の将校たちが負傷しただけですんだ。側近は危険だから予定行事のキャンセルを勧めたが、大公はそれを拒んだ。45分後、大公の車は将校を見舞うため病院に向かっていた。しかし、ドライバーが道を間違えたのに気づき、バックするために停止したその瞬間、カプリコ・プリンチプが大公と妃に2発の銃弾を撃ち込んだ。妃は即死、大公は10分後に亡くなった。その日は二人の結婚記念日だった。
 サラエボ暗殺事件 1914年6月28日 Wikipedia
サラエボ暗殺事件 1914年6月28日 Wikipedia
この暗殺事件の背後には、オーストリア帝国内のセルビア民族の独立を唱える秘密結社「黒い手」があった。警察の調べで、この組織にオルグされた6人の若者がそれぞれ銃と爆弾をもって大公を待ち受けていたこと、セルビア参謀本部の諜報担当大佐が事件に関与していたことが明らかにされた。どの程度、セルビア政府がこの陰謀に関与していたかは今でも謎だが、凶器はセルビア軍が提供したことが判明し、オーストリアはセルビア制裁を決意する。
事件から6日後の7月5日、オーストリアの使節が皇帝フランツ・ヨーゼフ1世とレオポルト・ベルヒトルト首相兼外相の書簡を添えてベルリンに到着した。首相書簡には「暗殺事件は巧みに練られた陰謀の結果である。その背後にはベルグラード(セルビアの首都)がいる。バルカン半島から(セルビア政府を中心とする)大セルビア主義を駆逐しなくてはならない」とあり、軍事制裁への同意を求めていた。当時ドイツとオーストリアは軍事同盟国だったが、力関係からいうと新興帝国ドイツが兄貴分だった。オーストリアの使節は、ドイツ皇帝(カイザー)ヴィルヘルム2世に会う。オーストリア皇帝と首相の書簡を読んだカイザー髭の皇帝は、午餐会の席で使節に「ドイツはオーストリアを全面的に支持する」と言った。これはオーストリアへの白紙委任状であった。翌日、カイザーは皇室専用ヨットでノルウェーのフィヨルドに暑中バカンスにでかけ、ベルリンに戻ってきたのは3週間後だった。
暗殺から10日後の7月7日、オーストリア・ハンガリー帝国閣僚会議が開かれた。ベルヒトルト首相は直ちに軍事制裁をすべきだと主張したが、ハンガリーのティサ首相は反対し、まずはセルビアへの要求事項を書いた書簡をおくるべきだと主張した。皇帝はティサ首相案を支持し、その段階では最後通牒はださないことになった。7月14日、両首相は会談し書簡の内容に合意した。暗殺から21日目の7月19日、こんどはベルヒトルト首相がティサ首相に、数日後にロシアで開かれる露仏首脳会談の結果を待ってから書簡をだすことを提案し、1週間保留することになった。
暗殺から25日目の7月23日、サンクトぺテルブルグでフランス大統領レイモン・ポアンカレとロシア皇帝ニコライ2世はセルビアへの無条件支持を表明した。同日、オーストリアはセルビアに書簡を送り、48時間内に回答するように求めた。しかし、書簡が届くことが通知されていたにもかかわらず、セルビアのニコラ・パシク首相は首都を離れていた。ベルグラードに戻ってきた首相が閣僚会議を開いたのは、書簡が届いてから30時間後であった。暗殺から27日目の7月25日朝、激しい議論のあと、セルビアはオーストリアの10の要求を全面的にのむことでほぼまとまり、これで決着かと思われた。
しかし、その日の午後、ロシア皇帝が軍に部分動員令(総動員令は戦時体制への移行宣言だから、部分動員はその前段階)をだし、事態は急変する。このニュースを知って、セルビア首相と閣僚は強気になり、6つの要求に条件をつけ、最も重要な要求(オーストリアの役人がセルビアで暗殺事件の調査に参加する)を拒絶する回答書が作成された。この書簡はセルビア首相からオーストリア大使に渡され、ウィーンに届けられた。
この書簡を受け取ったオーストリアは軍事制裁の準備にかかった。その頃、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世はバカンスからの帰途の船上で、ポアンカレ仏大統領もまた仏露首脳会談のあと帰国途上にあった。7月26日、英国外相エドワード・グレイは、このままでは大国を巻き込こんだ戦争になることを恐れ、緊急4ヵ国会議(英独露仏)を開くことを提案する。グレイ案だけであったら、事態打開の可能性もあったのだが、ロシアがオーストリアとの直接交渉を提案し混乱、危機回避のための会談は流れた。
28日、オーストリアはセルビアに宣戦布告をする。29日、ベルリンのドイツ皇帝ヴィルヘルムは事態が急速に悪化しているのを憂慮し、ロシア皇帝ニコライに「ロシアがオーストリアとセルビアの紛争に傍観者の立場をとることで、ヨーロッパがかつて体験したことのない恐るべき戦争を回避できるのではないか」「仲介をする用意がある」との英文電報を打った。(ヴィルヘルムは英国のビクトリア女王の孫で、ニコライの妻は女王の孫娘だったので従兄弟だった。彼らは互いをウィリー、ニックと呼び合っていた)これを読んだニコライは直ちに陸軍大臣に電話をし、総動員令を解除するように指示した。そのとき午後9時30分、サンクトペテルブルグ中央郵便局から総動員が電報でロシア全土に発令される直前であったが、危機一髪で間に合った。
これで、交渉への道が開けたと思われたが、状況は再び暗転する。

ドイツ皇帝(左)とロシア皇帝 軍服を交換して着用するほどの仲だったが、
ヨーロッパを救うことはできなかった。 US Library of Congress
ニコライが総動員発令を解除した翌日の30日、ロシアの外相、陸相、参謀総長、は長時間かけて情勢を分析し、もはや戦争は回避できない、総動員をかけないとロシアは不利になるとの結論に達した。午後遅く、セルゲイ・サゾーノフ外相はニコライに会い説得にかかった。皇帝は「これは難しい決定だ」「しかし、わたしが決める」と不機嫌そうに言ったという。会見を終えた外相はニコライ・ヤヌシュケーヴィッチ参謀総長に電話をして、総動員発令を伝え「電話を壊してもいいぞ」と言った。皇帝との会談の前、陸相が彼にこんど総動員がかかったら、電話を叩き潰して連絡を絶ち、再びキャンセルができないようにするよ、と言っていたからだ。
その日、ドイツでも同様のことが起こっていた。30日、ヴィルヘルム2世がロシアを刺激するなとオーストリアを説得していたが、ヘルムート・モルトケ参謀総長(彼の叔父はモルトケ元帥)はロシアの動きに神経を尖らせていた。オーストリア軍が対セルビア戦に投入する師団の移動によって、東部の守りが手薄になる、総動員をかけなければロシアに対抗できないと考えた彼は、オーストリアの参謀総長に次のような電報を打った。「オーストリアはただちに総動員をかけるべきだ、われわれもやる」。これは明らかに、総動員に慎重だった陸相の権限を犯す越権行為であった。この電報を読んだオーストリア首相は総動員令を準備し、翌日、皇帝の署名を得て直ちに公表した。
ロシアが総動員をかけ、それにオーストリアが続いたので、ドイツが目論んでいたロシアとオーストリアの直接交渉の望みは断たれた。ドイツはロシアに12時間以内に総動員を撤回しなければ、われわれも総動員をかけると通告した。さらにドイツはフランスに「総動員は戦争を意味するわけだから」それはやらずに、中立宣言を18時間以内にしてほしいとの最後通牒をした。
これは、皇太子暗殺事件から34日の出来事である。歴史家キーガンは、事件から5日目には、オーストリアは確固とした証拠を集め犯人は告白していたのだから、セルビア制裁を一挙にやるべきだった、と書いている。ドイツと相談したりせず、勇気をもって断行していたら、国際世論はオーストリアを支持していたので、セルビアの保護者を任じるロシアも手はださなかっただろう。早期に決着をつけていれば、地域紛争で済んでいたのに、時間が経てば経つほど、大国の関与が大きくなり威信をかけた対立となった、その結果、誰もがやりたくなかった戦争になった、とキーガンは分析している。第一次世界大戦は国家の威信という怪物が起こした戦争といえるのではなかろうか。
暗殺事件から35日目の8月1日、ドイツはロシアに対して総動員をかけ、フランスもほぼ同時に総動員をかけた。2日、ドイツは中立国ベルギーにフランス攻撃のため領土通過の要求をした。拒否されれば、敵国とみなすとの最後通牒付きであった。3日、要求を拒否されたドイツはベルギーに侵攻した。4日、中立条約を破ったドイツにイギリスは宣戦布告した。その結果、英仏露はドイツと戦争状態に入った。
英国の歴史家T.J.Pテイラーは、第一次世界大戦は時刻表戦争(Timetable War)だったと言っている。当時の軍事作戦で最も重要なことは、総動員をかけたあと、数百万の兵士をいかに迅速に前線に送るかであった。テイラーは、ドイツ参謀本部が練りに練った軍事作戦が、まるで鉄道時刻表のように着実かつ正確に実施されると信じて、戦争を開始したと皮肉っているわけだ。
ドイツの戦争計画を立案したのは参謀総長アルフレート・シュリ―フェンだった。仮想敵国フランスとロシアに対して、ドイツがいかに戦うかを、彼は現役時代も退役してからも地図と動員表をにらみながら作戦計画書を精密化していた。
1906年に立案されたその基本計画はシュリ―フェン・プランと呼ばれ、20世紀で最も重要な公式文書の一つだといわれている。ドイツの中立国ベルギー侵攻はそのプランに従ったもので、作戦開始から6週間でフランス軍を破り、パリを占領するという短期決戦計画だった。しかし、ドイツ軍はパリに30キロまで迫ったが、マルヌの会戦でフランス軍に敗れ退却、戦争は4年以上をかけた塹壕戦と毒ガスの人類史上で最も野蛮な戦いになった。

キュ―バ危機 空軍幹部と協議するケネディ大統領 1962年10月18日 CIA
軍人が立案した戦争計画はシナリオ通りにはいかない。戦争がいったん始まると何が起こるかわからない。第一次世界大戦は避けられる戦争だったが、大国のリーダーと軍部の読み違いで悲劇になった。このことを、バーバラ・タックマンは1962年のピューリッツアー賞作品『8月の砲声』で、ドキュメンタリー映画のように鮮やかに描いている。
当時、全米でベストセラーになったこの本をジョン・F・ケネディ大統領は、米ソが核戦争寸前までいったキューバ危機(1962年10月)の直前に読んでいた。
彼がこの本から学んだ歴史の教訓は、相手の意図を誤解し、意思の疎通ができず、状況判断を誤ると、予期しない事態に進展し、戦争になることがある。戦争になると、その結果は誰にも予測できない、というものだった。
『8月の砲声』のなかで、彼の印象に最も残った箇所は、大戦後に交わされた二人のドイツ人政治家のやりとりだったという。「どうしてあんな事になったのですか」(若い政治家)「それがまったくわからないんだ」(老政治家)
ケネディは状況判断を誤って、核戦争になることを恐れていた。タックマンは、総動員令がでると、軍のマシーンは戦争計画にしたがって、自動的に突き進んでいくことを描いているが、ケネディはその危険性に注目したにちがいない。
ソ連がキューバに核ミサイルを設置したことへの報復として、キューバを侵攻せよ、空爆せよ(カーティス・ルメイ空軍参謀長はキューバに核爆弾落下を提案)と軍部は主張したが、ケネディはそれを退けている。ペンタゴンのシナリオにしたがうと、事態がエスカレートし危険だと彼は考えたのだ。ケネディが打った手は、キュ―バ海域を封鎖して追加の軍事物資を積んだソ連船のキューバ上陸を阻止することだった。海上封鎖宣言をする一方で、彼はフルシチョフに書簡をだし、核戦争を回避するための妥協案(キューバからの核ミサイル撤去と米国のキュ―バ不侵攻、トルコの米軍核ミサイル撤去)を提案し、フルシチョフはそれに同意した。これで、人類は核戦争による自滅から救われた。
ケネディがキューバ危機に際して示した優れたリーダーシップは、危機管理のモデルと言われている。彼は、国家安全保障委員会のメンバー(主要閣僚と軍のトップ13人)に自由に発言させ、複数の対応策のなかから選択するスタイルをとった。キューバ危機に関する最も優れた著作といわれるマイケル・ドッブスの“One Minute to Midnight”(終末まであと1分)2008年刊を読むと、委員の大多数はキューバ軍事制裁を主張し、ケネディが孤立していたことがわかる。ケネディも一時は制裁に傾いたが、瀬戸際で思いとどまった。2012年に情報公開された文書で、ケネディが「今朝、わたしは不本意ながらキューバの核ミサイル基地を攻撃・破壊する命令をだした」という演説草稿を準備していた事実が明らかにされている。紙一重とはこのことだろう。
ケネディは歴史を意識した大統領だった。その証拠に彼は、キューバ危機13日間の国家安全保障委員会のやりとりを密かに録音させていた。この録音テープのおかげで、われわれは、人類存亡の危機に直面したときの米国のリーダーたちの生の声を知ることができる。国家の命運を賭けた重大な決定をする、どこの国の大統領、首相も歴史の審判を受ける覚悟がいる。ケネディはその審判を受ける覚悟があったから、録音をとったのだろう。そして、後世に国家秘密が公開されなければ、われわれは歴史から学ぶことができない。
いま日中は尖閣をめぐって対立している。相互不信はエスカレートし、対話・交渉で問題を解決する道は閉ざされているように見える。第一次世界大戦の教訓のひとつは、いくら対立しても外交交渉は続けなくてはならない、という点だ。首脳会談ができないなら、秘密交渉をやるべきだ。もつれた縄を解きほぐす第一歩は、あの小さな無人島をめぐって国家の威信をかけて戦争をするなど愚かなことだ、と日中が確認・合意することだろう。
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール
土野繁樹(ひじの・しげき)
フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て
「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |