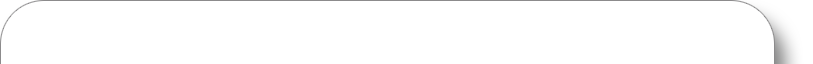土野繁樹
Wikipedia
筆者は昭和16年に産声をあげたから、真珠湾攻撃の年に生まれたことになる。月日はめぐり、今年はあの奇襲攻撃(1941年12月8日)から72年目になる。大学生になり日本の命運を分けたあの日、日本中が歓喜の声に包まれたことを知った。
朝日新聞は真珠湾攻撃の翌日、「米海軍に致命的大鉄槌/戦艦六隻を轟沈大破す/空母一、大巡四をも撃破」と大見出しを躍らせ、その紙面に載った日米交渉経過に関する記事には「米、終始独善を固執」という見出しをつけている。朝日新聞は米国を「独善的」と断定していたわけだ。
大多数の作家・知識人は、このニュースを庶民とともに、これでスッキリした、朗報だと受け取った。なかでも作家・伊藤整(戦後に『チャタレー夫人の恋人』を訳す)は国粋主義者だった。開戦の日の日記に「大和民族が、地球の上では、もっともすぐれた民族であることを、自ら心底から確信するためには、いつか戦わねばならない戦い」と興奮して書いている。例外は『フランス物語』の作者・永井荷風だった。彼は開戦から数日後の日記に、電車のつり広告にある「進め一億火の玉だ」「鉄だ力だ国力だ」をつまらぬ文句だと言い、この戦争はだめだと言外に匂わしている。
首相・東条英機は「人間は一生に一度、清水(寺)の舞台から飛び降りなくては」と言い、その決断を自画自賛した。昭和天皇・裕仁は「虎口に入らずんば虎子を得ずだね」と内大臣・木戸幸一にその感想をもらし、木戸は「感激す」と日記に書いた。(『ドキュメント 太平洋戦争への道』半藤一利著PHP文庫)
わが家の書斎の本棚にウィンストン・チャ―チルの『第二次世界大戦』回顧録6巻(The Second World War Winston S. Churchill )がある。これは義理の父アーヴィドから譲り受けたものだ。アーヴィドは外国航路の大型客船の船長だった人で、隣人からキャプテン・ラーソンと呼ばれ親しまれていた。
第二次大戦中の1941年、彼が二等航海士として乗っていた英国商船がドイツのUボート(潜水艦)の魚雷攻撃にあい 沈没、救命ボートで脱出するときに敵機の機銃攻撃をうけたが、幸い弾は当たらなかった。
救助された彼はスウェーデン人の同僚とロンドンで一冬過ごすことになる。当時、英国の首都ロンドンはドイツ軍の空爆下にあった。毎晩(連続で56日間)、敵機の編隊がやってきて爆弾を落とし、街中が火に包まれる大空襲(Britz)の日々をアーヴィドは体験している。
ロンドン空爆でヒトラーはイギリス人の士気を挫き、英国上陸作戦を敢行するつもりだったが、逆に彼らの戦意を高める結果になりあきらめた。アーヴィドは生涯、この不屈のジョン・ブル魂に敬意を抱いていた。だから、チャ―チルの『第二次世界大戦』を大いなる関心をもって読んだのだと思う。
チャ―チルはこの著作で政治家として初めてノーベル文学賞を受賞(1953年)したのだが、スウェーデン・アカデミーの授賞理由は次のようなものだった。「彼の現代史をテーマにした作品には、深く密度の高い自らの体験と知識が溢れ出ている、そのスタイルは明晰でユーモアがあり寛容である。彼は英語の巨匠である。行動がともなった彼の言葉は、あの暗い時代に世界中の多くの人々に希望と自信を与えた」。
チャ―チルは恒例の記念晩餐会のスピーチで感謝の辞を述べたあと、いつものユーモアでワサビを効かしている。「わたしはこの受賞を誇りに思っている。同時に スウェーデン・アカデミーの選択に、本人がおどろいていること認めざるを得ない。この選択が正しいことを願っている。しかし、皆さんがなにも心配していないのであれば、わたしも気にしないことにしょう」(夫人代読)。
 ウィンストン・チャーチル Wikipedia
ウィンストン・チャーチル Wikipedia
さて、チャ―チルは回想録第3巻で日本について2章60頁を割いている。ここでは、二つのこと、チャ―チルの松岡洋祐外相宛の書簡(1941年4月2日)と真珠湾攻撃を知ったときの彼の反応(ロンドン時間12月7日)を紹介して、読者の参考にしたいと思う。
本論にはいる前に、時代背景を簡単に説明しておこう。ヨーロッパではヒトラーのドイツがほぼ大陸全土を制圧し、英国だけがその存続をかけてナチス軍と戦い、米国は戦争へは介入せず中立政策をとっていた。日本は前年の1940年9月に日独伊三国同盟を結び、英米との関係が悪化し戦争の可能性が語られはじめていた。
そんな状況のなか松岡は1941年年3月、外相としてヨーロッパ情勢把握のためにベルリンを訪れている。
「松岡のベルリン訪問の目的は、ドイツのヨーロッパ制覇の実態と英国侵攻作戦の開始時期を知ることであった」とチャ―チルは書き、戦後、米軍が捕獲したナチスの外交文書のなかにある松岡ミッションに関する記録を紹介している。以下 その要旨である。
3月27日、英国侵攻作戦についてリッベントロップ独外相は松岡に「ドイツは対英戦の最終段階に入った。速やかに英国を征服するつもりだが、もはや障害となるものはなにもない」と言い、ヨーロッパにおけるドイツ軍の圧倒的な強さを「陸軍はもちろん空軍力も英米に優り、Uボートの増産で英国の息の根を止めることができるだろう」と数字を上げながら説明している。さらにリッベントロップは、「枢軸国側はもはや勝利を手にしたのも同然だ。英国降伏は時間の問題だ」と言い放っている。
日独伊三国軍事同盟についてリッベントロップは「ヒトラー総統は、日本ができるだけ早く英国に宣戦布告をすることを望んでいる。日本がシンガポールを攻撃すれば、英国降伏を早める決定的な要素になる」と松岡に参戦を勧めている。
昼食後、松岡はヒトラーとの会談に臨んだ。冒頭、ヒットラーは松岡に次のように言った。「戦争がはじまって以来、ポーランドの60個師団、ノルウェーの6個師団、オランダ18個師団、ベルギーの22個師団、フランスの138個師団、英国の12-3個師団が屈服した」「もはや敵には枢軸国に抵抗する力はない」。そのあと長いモノローグが続いた。
ヒトラーの長広舌を聴いた松岡は、総統の忌憚のない見解に感謝する、大略においてその見解に賛成すると言い「日本は千載一遇のチャンスであると思ったら、決定的なかたちで行動を起こす」と語っている。さらに、個人的には日本はできるだけ早く参戦したほうがよいと考えているが、自分には決定する権限がない、帰国したら、その方向でベストを尽くすと言った。しかし、参戦についてはかなり躊躇があるようだった、とドイツの外交文書は記している。
松岡は当時、米国のタイム誌の表紙になるほど、国際的注目を浴びた外交官だった。チャ―チルは松岡を寸評して「彼は米国で教育を受けたが、強硬な反米主義者だ。ナチスとドイツの軍事力にいたく感銘を受けているようで、ヒトラーの呪縛にかかっている」と厳しい。
チャ―チルは前述の日独会談のやりとりは知らなかったのだが、その会談の重要性はよく分かっていた。そこで、彼は松岡外相宛の書簡を書くことにした。一国の首相が外国の外務大臣にその国策について手紙を直接書くのは異例だが、彼はそんなことは気にしていない。
「大日本帝国政府と国民の喚起を促すために、敢えて貴殿宛にこの手紙をだすことにした」ではじまるこの書簡で、チャ―チルは8つの質問をしている。そのなかの3つを挙げてみよう。
ドイツは英国を占領できると思うか?その結果を待ってから行動したほうが、日本の国益にならないか?
ドイツ軍とゲシュタポによって占領された諸国は将来、ドイツに友好的になるだろうか、反感をもつだろうか?
1941年の鉄鋼生産力は、米国7500万トン、英国1250万トンで合わせると約9000万トンになる。日本の鉄鋼生産量は700万トンだ。もしドイツが第一次世界大戦と同様に敗北するとしたら、日本は一国で戦うことになるが、その生産量では足りないのではないか?
これは、まるで新聞記者の鋭い質問のようだ(彼は若い頃、従軍記者体験がある)。書簡の最後にチャ―チルは、これらの質問への日本の答えが破局回避、英米との関係改善であることを望む、と書いている。
ベルリンからの帰途、モスクワで日ソ中立条約を結び、意気揚々と帰国した松岡は4月22日付で、チャ―チルへ以下の内容の返事を書いた。
日本の外交政策はすべての事実を偏見なく吟味し、わが国が直面している状況のすべてを慎重に分析して決定される。その究極の目的は八紘一宇の実現である。八紘一宇は征服、抑圧、搾取のない平和な世界を意味する。その実現にあたっては人種的立場(アジア人のためのアジア)を勘案する。ひとたび、政策が決定されれば、決意をもって実行されることになる。しかし、状況の変化をも見逃すことなく細心の注意をもって決定されるであろう。
この返信で松岡はチャ―チルの懸念は大きなお世話だと仄めかし、8つの質問には触れず八紘一宇の哲学で国策を決定すると言っている。両者の共通点は八だけであった。
ヒトラーと松岡洋祐 Wikipedia
1941年12月7日(ロンドン時間)、日曜の夕刻、チャ―チルは駐英米国大使ハリマン夫妻をロンドン郊外の自宅チャートウェルに招いていた。ラジオ・ニュースを聴いていたハリマンが、日本が米国を攻撃したようだと言った。間もなく執事が部屋に入ってきて、そのニュースは本当のようですと確認した。一瞬、沈黙が支配した。
チャーチルは直ちにルーズベルト米国大統領に電話をし、次のような会話を交わした。「大統領閣下、日本についてのニュースは本当ですか?」(チャ―チル)「本当です。彼らは真珠湾を攻撃しました。今やわれわれは一蓮托生です」(ルーズベルト)「これで、事が簡単になりました。神のご加護を」(チャ―チル)
チャ―チルは回想録に「真珠湾攻撃は息をのむような世界的大事件だった」と書いている。
翌日の12月8日、チャ―チルはルーズベルトの外交顧問ハリー・ホプキンズに手紙を書いた。
わたしはこの事態を予測できなかった。日本の軍事力を正確に把握していなかった。しかし、今や、アメリカが参戦し死を賭して戦うことになった。ダンケルク、フランスの降伏,オラン港事件、侵攻の脅威、Uボート戦争と、17か月間におよぶ英国の孤独な戦いのあと、これで、結局、われわれは勝ったのだ!
英国は生き残る。戦争がどれほど長くなるかは分からない。ヒトラーの運命は決まった。ムッソリーニの運命も決まった。日本は粉砕されるだろう。あとは圧倒的な戦力を行使すればいいだけだ。英米ソの戦力は、敵の数倍ある。米国を侮る人々がいる。彼等は、アメリカ人は団結できない,血を見るのを嫌がる、と思っている。そんなことはない。わたしのなかに流れているアメリカ人の血(チャ―チルの母親はアメリカ人)が知っている。
友人エドワード・グレイ(第一次世界大戦時の英国外務大臣、同時期チャ―チルは海軍大臣)が30年前に言った言葉を思いだす。「米国は巨大なボイラーだ。いったん火がつくとそのパワーには際限がない」。
チャーチルは国策を決定するにあたって、ビスマルクを引き「常に相手の立場になってみることが必要だ」と言っている。「相手国のことを十分にかつ同情心をもって理解すればするほど、その政策の正しさの確率が高まる、相手国に関する知識が深ければ深いほど、なにをやればよいかが明らかになる」と自他を客観視してみることの重要性を説いている。
その原則から言うと「日本の真珠湾攻撃は、米国が自己防衛のためにかつてないほどの団結をすることを無視した、単純極まりない問題解決策だった。アメリカ人にとっても、わたしにとっても、日本が米国を攻撃することは自殺行為だと思えた。しかし、政府も国民も常に理性的な決定をするわけではない。時に、狂気の決定をする。真珠湾攻撃について、わたしは、ためらうことなく、日本は気が狂った、信じられない、と繰り返し言ってきた。いくら『相手の立場』になってみても、不可解な決定だったからだ」とチャーチルは真珠湾攻撃の無謀さを断じている。
筆者は、チャーチルの真珠湾攻撃の章を読みやりきれない気持ちになった。日本中が沸きかえっていたあの日、チャーチルは、連合軍の勝利を確信し、日本は狂気の決定をしたが故に敗北すると予言し、事実そのとうりになった。ということは、真珠湾攻撃は国益を守るための「自衛のための戦争」どころか、日本人310万の命(軍人230万人の戦没者のうち餓死者が60%。市民80万人が死亡。米英と中国などの連合軍の軍人・市民の死者は推定2000万人)を犠牲にした「自殺行為」だったということになる。真珠湾攻撃のツケはあまりに大きかった。
日本は清水の舞台から飛び降りて半身不随になり、虎口に入って虎に食われたわけだ。なぜ、こんなことになったのか。アメリカの国力と戦闘精神を見くびったことが最大の理由だろう。日独伊三国同盟が結ばれたとき、この国が危険な曲がり角を曲がったなどと思う日本人はいなかった。政府・軍部による厳しい言論統制の時代、国民は洗脳され、世界を知らず、アメリカのことをなにも知らなかったのだ。愛国、反米を煽った新聞の責任も大きい。なにより、自国を客観視する能力がない指導者の犯した罪は極めて重い。
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール
土野繁樹(ひじの・しげき)
フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て
「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |