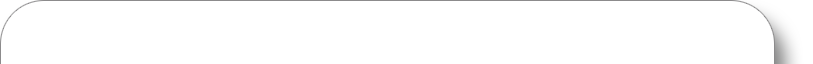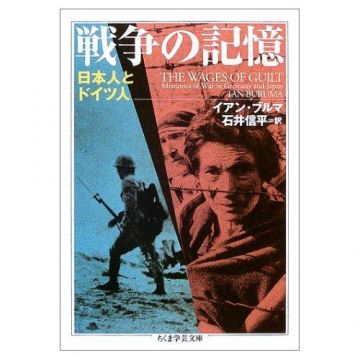土野繁樹

オラドゥ―ルの遺跡 Wikipedia
フランス人ならオラドゥ―ル村のことを誰でも知っている。フランスがドイツの占領下にあった1944年6月10日に起こったSS(ナチス親衛隊)による村民虐殺事件は、70年あとの今でも、この国の人々の記憶に深く刻み込まれている。なぜなら、オラドゥ―ル村が事件直後の姿のまま保存されているからだ。
わたしもこの村を7,8年前に訪れたことがある。広い廃墟の跡には、ほこりを被ったミシン、崩れかかった郵便局跡、錆びたプジョー車と電車の軌道があった。ドイツ兵は女性とこども400人を教会に閉じ込め機関銃で殺し放火したが、その教会の壁には銃弾の跡が残っていた。あれほどやりきれない気持ちになったことはない。
戦後、仏独は和解し、両国は深い信頼関係で結ばれている(世論調査をすると、両国民とも相手国を最も信頼する国に挙げる)。だが、これまで、ナチスの暴虐を象徴するオラドゥ―ルの遺跡を訪れたドイツ首相や大統領はいなかった。ところが、9月4日、フランソワ・オランド仏大統領 の招待を受けてヨアヒム・ガウク独大統領がこの地を訪れ、ドイツ国民を代表して謝罪したのである。
残念ながら、このニュースを日本のマスコミはほとんど報道していない。1944年の夏、オラドゥ―ルで何が起こったのか、ガウク独大統領はどんな思いでこの地を訪れ、オランド仏大統領は彼をどのように迎えたのか、仏のルモンド紙、フィガロ紙、独のシュピーゲル誌などの報道と歴史家メリー・ファーマーの『受難の村・オラドゥ―ルの物語』(The Martyred Villege: The Story of Oradour 1999)をもとに、ドキュメンタリー形式でお伝えしよう。これは、独仏首脳の和解のためのたゆまない努力のストーリーでもある。
オラドゥ―ルはフランス南西部にある磁器の町リモージュから20キロのところにある。当時、村人は戦争とナチス占領の余波をほとんど受けることなく平和に暮らしていた。村にはカフェ、サッカーチーム、音楽クラブがあり、小学校には170人の児童が通っていた。オラドゥ―ルの語源はラテン語のオラトリアム( oratorium)‘ 祈りの場’だという。
1944年6月10日、土曜日だったので村は活気に溢れていた。その日は連合軍がノルマンディー作戦を開始してから4日目だったが、村人にとって別世界の出来事だった。小学校には午後から健康診断があるので児童が集まっていた。暑い日だったので小学校の窓が開け放たれていた。
午後2時、突然、ドイツ軍SS戦車師団ダスライヒの大隊がやってきた。昼食後ののどかな時の流れが破られた。ドイツ軍150人の将兵は村を包囲し、すべての住民に広場に集合するように命じた。生き残った6人の証言によると、みんな身分証明書のチェックだろうと思っていたという。
3時過ぎ、ドイツ軍兵士が女とこどもを広場から教会に移しカギをかけた。そのあと将校が広場に残っている200余人の男たちに向かって「武器弾薬がこの村に隠されているのを知っている。心当たりのある者は前にでよ」と言った。しかし、誰も出なかった。その将校は、村長に人質を指名してくれ、と言った。だが、村長はそれを拒否して、自分と息子たちを人質にとれと答えた。
将校は部下に命じて男たちを6つのグループに分け納屋に閉じ込めた。なにが起こるのかと、納屋のなかの男たちは不安になり、ひそひそ話を始めた。外では、ドイツ軍兵士が機関銃を銃座に備えつけていた。男たちの不安が高まった。やがて、誰かが‘打て’と叫んだ。機関銃の弾が飛び交い村の男たちをなぎ倒していった。兵士はまだ息のある男に止めをさしたあと、197人の死体を藁で被い納屋に火を放った。
5時頃、二人の兵士が教会の中に入り祭壇の上に大きな箱を置き、長いヒューズをそれにつなぎ点火してドアを閉めた。すると箱は爆発し教会の窓が吹き飛び、息ができないほどの煙に包まれた。大混乱となった教会のドアを開けた兵士は、女こどもに銃弾を浴びせかけた。女性240人、こども205人が殺された。彼らは死体に燃えるものを被せて、信徒席に火をつけて立ち去った。
6月11日の朝、オラドゥ―ルに残っているものは、焼けただれた農家、商店、住宅だけだった。642人の村人が抹殺された。
 SS戦車師団ダスライヒ 左は最高司令官ラムディンク commons.wikimedia
SS戦車師団ダスライヒ 左は最高司令官ラムディンク commons.wikimedia
このジェノサイドの背景には6月6日に始まった連合軍のノルマンディー上陸作戦があった。兵員300万を投入したナチス打倒のこの地上最大の作戦に呼応して、フランスのレジスタンスが立ち上がり列車転覆、通信遮断、ドイツ軍襲撃などゲリラ戦を展開する。とくにリモージュ地方でのレジスタンス運動は激しかった。
当時、オラドゥールの虐殺を犯したSS戦車師団ダスライヒは、参謀本部の命令でフランス南部トルゥ―ズ近郊からノルマンディーに北上中で、レジスタンス掃討も指示されていた。事件の前日には、師団の将校がレジスタンスに拉致されている。
なぜこんな大量虐殺が起こったのか?
アメリカ人歴史家ファーマーは、戦後開かれた裁判の記録、仏独両サイドの関係者による証言、事件に関する著作を精査して次のような結論をだしている。
オラドール皆殺し作戦の現場指揮官はSS大隊長アドルフ・ディエクマンだった。彼は親友の将校がレジスタンスの人質となり、殺されたことを知り激怒、上官の許可も得ないで大隊を引連れて、オラドゥ―ルに乗り込み報復をした。のちに村はレジスタンスとはなんの関係もないことが判明する。これが事件の真相だという。
事件の翌日11日、リモージュのSS本部でディエクマンから報告を聞いた上官スタドラー連隊長はショックを受け、女こどもを殺したのか、これは軍法会議ものだぞ、と怒りを露わにしたが、彼はジェノサイドの責任をとらされることはなかった。というのも、他の上官たちはそれほど深刻なこととは思わず、良い将校、良き同志だったディエクマンは、レジスタンスの連中に教訓を与える任務を熱心にやり過ぎただけだ、と思っていたからだ。
ディエクマンは事件の3週間後、ノルマンディー戦線で米軍の弾丸に当たって死んだ。
1945年3月、フランス臨時政府の長だったドゴール将軍がオラドゥールを訪れ犠牲者を弔い、ナチスの蛮行を忘れないために遺跡をそのまま保存することを決めた。
1953年1月と2月、ボルドーの軍事法廷で事件に直接関与したSS将兵65人の裁判が行われた。そのうち21人が出廷したが、他の被告はドイツにいたので法廷に立つことはなかった。21人のうちドイツ人は7人で、14人はアルザス出身のフランス人だった。40年6月ドイツがアルザス地方を併合したあと、彼らはナチスの軍人として各地を転戦していたのである。彼らはドイツ人とは別の法廷で裁かれた。
20名に有罪の判決が下った。しかし、アルザス出身兵士に対する死刑から懲役までの判決に、アルザス人は猛烈に抗議した―彼らはナチスに強制されて軍役についた者だ、もし彼らがオラドゥールの村で上官の命令に従わなければ、彼らは射殺されていただろう、という同情論からだった。
判決のあと、アルザス選出の議員のイニシアチ―ブで国会に恩赦法案が提出され、賛成311、反対211、棄権83で可決された。オラドール村とリモザン県の人々は、これは国家のわれわれに対する裏切りである、と激しく抗議し、戦功十字賞を国に返却する人々が続出、賛成票を投じた議員の名前がオラドゥ―ルの廃墟前に掲示された。10年間その掲示版は置かれたままだった。
1962年、ドゴール大統領が村を訪れ、村と国の関係は修復された。しかし、ボルドーの法廷で有罪判決をうけたドイツ人(裁判欠席)が、ドイツでなんの咎めもなく暮らしていることへの村人の憤りは解消されなかった。
SS戦車師団ダスライヒの最高司令官ハインツ・ラムディンクはボルドーでの欠席裁判で死刑を宣告されたが、西ドイツはフランスへの送還を拒否したので、裁判にかけられることもなく長い間デュッセルドルフで建築業を営んでいた。のちに両国政府は西ドイツ法廷で彼を裁くことに合意したが、彼はその前に死亡した。そのあと西ドイツ法廷で事件に関与したSS将兵は裁判をうけたが、懲役数年か証拠不十分で無罪となった。
1999年、シラク大統領がストラスブール(アルザスの首都)市長を伴ってオラドゥ―ル記念館開設のため村を訪れた。その日オラドゥール村長とストラスブール市長は握手をした。半世紀後の和解だった。(その年、シラクは戦時中、ヴィシー政府がナチスのユダヤ人迫害政策に協力し、在仏7万人のユダヤ人を死の収容所に送ったことを正式に謝罪している)
 教会跡で オランド仏大統領、オラドゥ―ルの生き残りエブラ、ガウク独大統領(左から)Le Figaro
教会跡で オランド仏大統領、オラドゥ―ルの生き残りエブラ、ガウク独大統領(左から)Le Figaro
今年の5月、ドイツのライプニッヒで開かれたドイツ社会民主党創立150周年の式典にオランド仏大統領が招待された。その席で、オランドがガウク独大統領に訪仏を要請すると、ガウクは、それはありがたい、公式訪問をしてどこか両国にとって象徴的な場所を訪れたいと言った。するとオランドは「それでは、オラドゥールへ一緒にいきませんか」と誘うと、ガウクは迷うことなく「そうしましょう」と答えた。
ふたりの大統領にとってオラドゥールは無縁のところではなかった。かつてオランドはオラドゥール村から10キロ離れたチュールで町長をしていたが、そこもまたナチスの犠牲になった所だった。オラドゥール虐殺事件の前日、SSはレジスタンスへの報復として99人の町の人々をチュールの広場で公開処刑している。前述のSS最高司令官ラムディンクは絞首刑の様子をカフェで葉巻をくわえて眺めていたという。
ガウクは東ドイツ生まれで、ベルリンの壁が崩壊する前はロストックの牧師だった。彼の父親は船長だったが、反ソ活動の容疑で25年の懲役の判決を受けシベリア送りとなった(5年のちに釈放)。少年時代のその体験が全体主義への不信のもとになったと彼は語っている。
東西ドイツ統一後に彼は国会議員になり、旧東ドイツの秘密警察シュタージのアーカイブを管理する2000人の組織の責任者になった。膨大な量のアーカイブ(ファイルを並べると111㎞)のなかには政治的爆弾になる文書もあったが、彼は共産主義の犯罪を調査する仕事を10年間、公平かつ厳格にやりドイツ国民が最も信頼する男になった。その後、政治家を辞め共産主義とナチスの犯罪を追及する財団「デモクラシーのために忘れない」の代表となった。
9月4日午後、太陽が輝く雲一つない紺碧の空の下、白髪のガウクはオランドと共に鎮痛な面持ちでオラドゥールの広場に立っていた。そこは59年前、SS兵士に村人が集められた場所であった。広場には虐殺を逃れた6人の一人ロベール・エブラ(88歳)がいた。
当時18歳だった彼は、二人の大統領を廃墟に案内しながら、機銃掃射を浴びた男たちの死体の下にいて奇跡的に助かった、と語っている。(「長い間、ドイツ人への憎しみと復讐心がわたしの心から離れることはなかった。だが、彼らと和解する時が来た」と母親と妹を殺されたエブラはガウクに会う数日前に記者に語っている)
オランドとガウクとエブラは、あの忌まわしい虐殺の現場だった教会の祭壇の前で、互いの手を握って犠牲者の霊に黙祷を捧げた。忘れがたい和解の光景だった。
オラドゥ―ル記念館を訪れたガウクは涙ぐみながらゲスト・ブックに次のように記帳した。「恐怖とショックと嫌悪の気持ちで、わたしはドイツ軍の犯罪に向き合った。わたしはこの招待を謙虚に感謝の念をもって受け入れた。今日のドイツは(昔とは)異なる平和な統一国家であることを証言する。これは変わることはない。ヨアヒム・ガウク」
記帳し終わるとガウクはすこし躊躇いながら、オランドの肩を抱いた。二人は長い間互いの肩を抱きあったままだった。それにエブラが入って三人の輪ができた。
オランドは次のように言った「今日のあなたの訪問は両国の友情を確認するものだ。そしてこの友情は全世界の模範であることを示している。世界のどこであろうと人権蹂躙には敢然と立ち向かおう」。
この和解のドラマはガウクのような経歴のある大統領だから可能であったともいえる。ドイツの大統領は名誉職だから権限はない。しかし、国家元首として象徴的な行動をとることで、国民の意思を伝えることができる。ガウクは信念をもってこれを実行し、オラドゥ―ルの人々は彼の真摯な態度に心を開いた。
フランスのメディアは例外なく、あたらしいドイツを代表する彼の心からの謝罪を歓迎し、オラドゥールの和解と報じていた。ドイツのシュピーゲル誌は‘辛い過去、ドイツ大統領がナチスの虐殺の場を訪問’の見出しでその日の光景を伝え、大統領の勇気を称えていた。
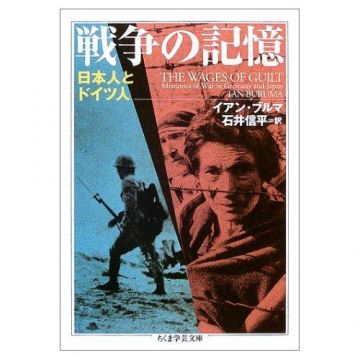
オランダ人ジャーナリスト・イアン・ブルマが書いた『戦争の記憶―日本人とドイツ人』(The Wages of Guilt :Memories of War in Germany and Japan 1994 ちくま学芸文庫)という本がある。わたしがTBSブリタニカの編集者時代に、親友だった石井信平君(3年前に亡くなった)の名訳で刊行した本なので感慨深い。
この本のテーマは、敗戦国の国民である日本人とドイツ人が過去からなにを学んだか、いかに過去を忘れようとしているのか、戦争責任とは何か、愛国心とは何か、である。
日本語とドイツ語に堪能なブルマが現場(アウシュヴィッツ、広島、南京、知覧、花岡など)と戦争体験者を徹底的に取材したこのルポルタージュの傑作をわたしは再読し、日独の対応のちがいを改めて考えさせられた。
たとえば、日本の学校では現代史は学期末に駆け足で学ぶだけだが、ドイツの学校ではナチスについて60時間学ぶという。もちろん、ナチス・ドイツ軍の暴虐と日本帝国陸軍を同列に置くことはできない。しかし、過去から学ぶという姿勢の差は明らかだ。
20年前に刊行されたこの本を読んで、わたしは日本人の戦争の記憶はあの頃よりいびつになったという感を深くした。その当時でも、‘日本はなにも悪いことをしていない’と主張する石原慎太郎や小林よしのりを支持する人はいたが、今日ほど多くはなかつた。
安部晋三首相もいびつな戦争の記憶をもつ一人である。彼は国会で「侵略という定義は学会的にも国際的にも定まっていない。国と国との関係でどちらから見るかで違う」と答えたが、これには仰天した。
他国に武力で攻め入り、支配すれば侵略である。日本が韓国、中国、欧米の植民地であった東南アジア諸国を侵略したのは自明の理だと思うのだが、彼は侵略の定義はないと言う屁理屈で過去の過ちを否定しようとする。侵略された国々が反発するのは当然だろう。中国政府は民衆の反日ナショナリズムを煽り、政治的に利用しているのは事実だが、だからと言って侵略の事実は変えようがない。
ちなみに国連は「侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全もしくは政治的独立に対するまたは国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使である」(1974年)と明快に定義している。
安部首相の歴史観は国際社会で支持されることはないだろう。この倒錯史観が国策に反映されると、将来、世界のなかで日本が孤立する可能性もある。われわれは歴史の事実に謙虚に向き合うべきだ。
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール
土野繁樹(ひじの・しげき)
フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て
「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |