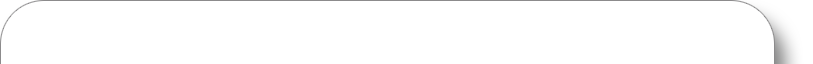土野繁樹

わが芝刈り風景
今年のドルドーニュ地方の夏は異常に暑い。先月、気温が40度まで上がり、地方紙が過去100年間で最高と報じていた。冬も例年より寒く、春は雨ばかりだったから、異常気象とはこのことだろう。
7月中旬から毎朝約2時間、庭の手入れをしている。サラリーマン時代の背広とネクタイに代わって、作業服に着替え、野球帽を被り、手袋をつけ、いざ出陣!(ユニフォームは人を任務遂行に駆り立てます)
2000坪の庭だから、作業はいくらでもある。基本は芝刈りと草むしりだ。芝刈り機にスウィッチを入れると、ホンダのエンジンが音をたてる。花壇がある平坦部分は楽なのだが、スロープ部分はきつい。昨年の夏は芝刈り機を前進させる機能が故障していたので、坂の作業は重労働だった。(‘人生は重荷を背負うて坂道を行くが如し’(徳川家康)の心境でありました)
草むしりは3mあるシーツに腰かけて作業する。花と樹木に絡まっている雑草をとる手仕事は単純作業だが、5分もすると無念無想(プラス無草)になれるからいい。禅に詳しい友人にこのことを話すと、「草むしりは禅の修行の一部だよ」言っていたから、期せずして参禅していることになる。(しかし、無草に熱が入りすぎ、奥方が植えた大事な花の茎を抜き取り、きついお叱りをうけました)
昔、京都の東山の麓にある法然院を早朝訪れたとき、若いお坊さんが作務衣を着て水の文様の砂紋引きをしていた。忘れられない光景だ。こんど帰国したら、あんな作務衣を買うことにしよう。
いまの作業服は古くなったズボンとシャツだから、究極のアップグレードになる。
パパドプロス音楽一家
パパドプロス夫妻からアぺリティフ(食前酒)の招待があった。夫妻は昨秋、静岡県伊豆熱川の山の上にあるわが家で一泊したことがある。ストラスブール大学の数学教授(幾何学専攻)である夫のアタナズ(写真左)は温泉に入ってよく眠れたとご機嫌だった。
夫妻と知り合ったのは、サン・ジャン・ドコール村の教会で行われる夏の木曜コンサートの会場だった。4-5年前のことだ。彼等の息子と娘2人は音楽家で、長女(写真右から2番目、3番目は彼女の夫)はパリ、長男(写真右から4番目)はリヨン、次女(写真左からは3番目、4番目は彼女の友人)はドイツのカールスルーエを拠点に国際的に活躍をしている音楽家だ。高校生の次男(写真左から2番目もバイオリン修行中)。
夏になるとこの家族は、わが家から7キロのところにある別荘に集まる。そこは奥さんのマリー・パスカル(写真右)の両親の家だという。「こんなに広い5000坪の庭の芝生を誰が刈りますか」と尋ねると「息子と娘がやるよ」とアタナズは言っていた。
今年の春、彼は中国の昆明の大学に招待されて講義をした。「中国人と日本人はちがうでしょう」(わたし)「まったく違いますね」(マリー・パスカル)「ぼくは違いを感じないね。数学者は世界のどこへ行っても同じだよ」(アタナズ)。それを聞いて、なるほどサイエンスの世界に国境はないのだなあ、と思った。
そんな世間山話をしていると、奥さんの両親が現れた。92歳の父親オトフィーユさんは、ティヴィエの町(わが家から車で10分のところにある)で40年間、医者をした人だ。25年前に引退してパリ郊外で暮らしているが、今でも町の年配の人は彼のことを‘いい医者だった’と懐かしそうに語る。
50年前に彼が創設した‘医療グループ’(開業医5人が同じ建物で患者を診察する)の活動は、いまでも同じ建物で続いている。そこの医者のひとりラぺロ二さんは、わたしと奥方が世話になっている人だが、彼の後継者だという。この偶然に驚いた。
オトフィーユ夫妻は数日後に結婚70周年を祝うという。おめでたいことである。
あとでマリー・パスカルから面白いエピソードを聞いた。彼女の父親の友人で先輩の医者が、哲学者で小説家のジャン・ポール・サルトルが幼いときに病気の治療をしたという。
さてそのサルトルは少年時代にティヴィエの町で数年暮らしたことがあるが ‘ティヴィエは退屈な町だった、あまりいい思い出はない‘と自伝の中で書いている。そのせいか、観光パンフレットにはサルトルのことは一言も書かれていない。町の不動産屋の2階の外壁に「1914年以前にここでジャン・ポール・サルトル(1905-80)が暮らした。ノーベル文学賞1964」と小さな銅板があるだけだ。
今年も村のコンサートに、パパドプロス家の長男デミトリ(ピアノ)、長女エレン(ピアノ)、次女マリー・クロディーヌ(バイオリン)の3人と次女の友人アレキサンドル(チェロ)が熱演し聴衆(各回100人)を魅了した。
初日は教会修復委員会の主催で有料(15ユーロ)だが、あとの2回は入場無料のコンサートだった(寸志は受け付ける)。3回のコンサートのあとには、教会の隣でレセプションがあった。ワインとジュース、手作りのケーキはパパドプロス家が提供したものだった。この家族は寛大だ。
彼等が演奏した主な曲はべ―ト―ベン、ブラームスのソナタだった。ソナタは序章からフィナーレまで4楽章あり、起承転結があるストーリーになっている。が、残念ながら二人の偉大な作曲家がこれらのソナタに込めた哲学的メセッージを、わたしは理解できたとは思えない。おそらく、音楽的、宗教的教養が足りないからだろう。
しかし、アンコール曲は音楽ファンなら誰でも聴いたことがある珠玉の名曲だったから、懐かしい人に再会したような気分になり心が浮き立った。
第一夜はジュール・マスネの‘タイスの瞑想曲’。4世紀エジプトの妖艶な娼婦タイスと修道士アタナエルの恋物語をテーマにしたオペラの一節だが、11世紀に建ったこの教会で聴くと、ひときわ味わい深い。祭壇のステンドグラスに映る青葉の緑が幻想的で美しかった。
第二夜はバッハの‘われ汝を呼ぶ、主イエスキリストよ’。美しく、深く心を揺さぶるこの曲を、姉のエレンと弟のデミトリがピアノ連弾で演じた。バッハの音楽は数学的だ、と町の美人図書館長でピアノを弾くブリジットが言っていたので、アタナズに聞くと、そのとうりだと言う。彼はバッハの大のファンで、いつも研究室で聴きながら幾何学のテーマに取り組んでいるという。
最終日は二女のマリー・クロディーヌとデミトリがエルガーの‘愛のあいさつ’を、最前席に座った祖父母オトフィーユ夫妻を前に演じた。エドガーが婚約者への贈りものとして作曲した真珠のような作品を、弟妹は彼らの結婚70周年記念へのお祝いに捧げたのではなかろうか。
宴会風景 正面がフォルニエさん 右の若い二人の女性は合唱団のメンバー
これまで禅的心境で手入れをしてきたわが家の庭で、木曜コンサートに出演する合唱団を招待して夕食会を開いた。主催はフォルニエさん(退役将軍)が幹事をする教会修復委員会(奥方はそのメンバー)で、客は英国からやってきた合唱団と委員会の面々をいれて25人。
料理とテーブルは出張宴会サービスの業者が担当し、アぺリティフと食卓の花は幹事が用意したので、当方は会場とキチンの提供だけだった。それでも、こんなに大勢の客ははじめてなので、いささか気をつかった。当日の朝、庭の中央の大型ポットの花が寂しいので、急遽、奥方と町まで車を走らせベゴニアを買いに行ったりした。
英国の合唱団の名は、村の住人ジュディが20年前にケンブリッジ大学の学生時代に創立したVoces Sacrae(聖なる声)という。バカンスを兼ねて村に滞在している聖歌合唱団は8人、指揮者はジュディ。この合唱団のコーラスはBBCで放送されたこともあるから、レベルは高い。団員は20代の女性音楽教師から40代の物理学者まで多彩だ。
まだ強い西日が射す午後7時過ぎ、奥方ヤードとわたしと娘の恵実(ストッホルム在住で夏休み来訪中)は客を迎えた。前日の奥方のアドバイス「こちらの人は、日本女性の着物姿は知っているけれど、男性の着物姿はめずらしいから着てみたら」に従って、わたしは意気揚々と和服姿で庭に立っていた。
すこし照れくさかったが、皆さん違和感はないようで興味津々、とりわけ顔見知りのマダム連の間で好評だった。和服を着ると日本の良き伝統を背負っている気分になるから面白い。それになぜか、雪駄を履き懐手をしていると、昔の東映ヤクザ映画、高倉健と池辺良が演じた「昭和残侠伝」を思いだしていた。
日が暮れて蝋燭の光のなかでのフランス語と英語が飛び交う夕食会は愉快だった。料理はドルドーニュの郷土スープからフォアグラのパテ、チョコレート・ケーキからコーヒーまでフルコースで充実していた。宴たけなわ、日が沈み冷え込んできたので10人の客にセーターとカーディガンを着てもらった。終わったのは11時過ぎ、皆さんご機嫌で大成功の宴会だった。
翌日の夕方、村に行くと合唱団の皆さん全員が店のテラスで紅茶を飲んで談笑していた。指揮者のジュディが「いいニュースがあるのよ。昨晩のパーティのあとでフィリッパとフレーザーが婚約したの」と言う。「おめでとう。記念すべきロマンチックな夜になってよかったわ」と奥方も嬉しそうだった。
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール
土野繁樹(ひじの・しげき)
フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て
「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |