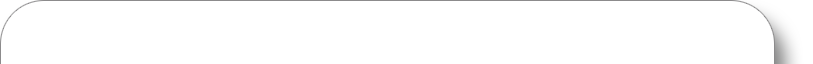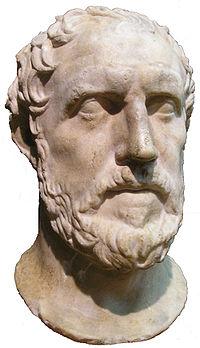土野繁樹
 |
| オバマと習の50分の散歩歓談 New York Times |
米国カリフォル二ア州の砂漠の保養地サニーランドで行われた米中首脳会談は異例ずくめだった。栄誉礼、公式晩餐会、歓迎行事なしで、ノーネクタイ。これまでの米中首脳会談の公式随員は双方20人で、その後ろにスタッフが控えていたが、6月7,8日の会談は6人と少数精鋭。ふつう首脳は、スタッフが準備したメモに従って発言するのだが、その場面はあまりなかったようだ。
バラク・オバマ大統領がこの非公式会談を提案すると、習近平国家主席は直ちに受諾したというからこれも異例である。なぜ、この会談が行われたのか。米中関係が貿易と軍事の二つの分野で対立が激化し、将来、望んではいない戦争になることを両国首脳が恐れているからだ。
ハーバード大学の政治学者グレアム・アリソン教授が、昨年8月、英国のフィナンシャル・タイムズ紙に寄稿した‘太平洋に姿を現したツキジデスの罠’という評判になったコラムがある。
ツキジデスは紀元前5世紀のギリシャの将軍で歴史家『ペロポネソス戦争史』の著者として知られる。その本で新興国アテネと覇権国スパルタの戦いを描いたツキジデスは「戦争を引き起こした究極の原因は、アテネの国力興隆へのスパルタの不安である」と記している。
この分析に注目したアリソンは、1500年以来、新興国家の挑戦とそれを受けて立った覇権国家の関係を調べてみた。すると、15の事例の中で11までが戦争になっていることを発見する。
新興国が力をつけ自信を持つと、覇権国は優位を失うことを恐れ、同盟国を巻き込んだ戦争への道を選ぶという歴史のダイナミックスを、アリソンはツキジデスの罠と呼ぶ。
彼は今回の首脳会談の前日、ニューヨークタイムズ紙に寄稿し次のような提言をしている。
100年前もツキジデスの罠のパターンが繰り返された。1914年、新興国ドイツはそれまで世界を支配してきた英国のパックス・ブリタニカに挑戦し、第一次世界大戦がはじまった。結果は3600万の死傷者をだす大災禍だった。
これが歴史の法則とすれば、21世紀の超大国アメリカと未来の超大国中国の軍事衝突は避けがたいということになる。ツキジデスの罠から逃れる方法はあるのだろうか。
米国のナンバー・ワンは自明の理であると考えるアメリカ人は、驚異的な中国の興隆(マッケンジー世界研究所によると、英国の産業革命と比べると中国のその規模は100倍でスピードは10倍だという)を事実として率直に認め、これは米国が直面する歴史的挑戦であることを認識すべきだ。
ビジネスのトップも官僚も政治リーダーも、従来通りのやり方で事足りると思っていると、過去の例から言うと罠にかかる可能性が高い。したがって戦争を回避するためには、米中の指導者による尋常ではない努力がいる。カリフォルニアの首脳会談1回だけではなく、一世代かけた努力がいると考えるべきだ。
オバマと習は直面する問題に取り組むだけではなく、ツキジデスの罠にはまらないためには、両国がなにをすべきかを協議しなくてはならない。
中国もその危険性を認識しているから希望はある。たとえば、10年前、中国の最高決定機関・政治局は‘15世紀以来の主要国発展に関する歴史的調査’というテーマで討議をしているからだ。
それに「中国の指導者は、軍事面ではアメリカに比べて圧倒的に劣っているので、挑戦は不毛であることを知っている」とリーカンユー(シンガポール元首相)が言うように、彼等は現在の自国の実力を知っている。
以上がアリソンの提言と分析だ。彼はクリントン政権の国防次官補を務めた経歴がある、外交・国防政策に関して影響力をもつ学者だから、オバマはペロポネス戦争の教訓を十分理解しているにちがいない。
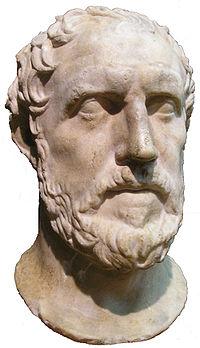 |
| ツキジデスの胸像 Wikipedia |
オバマと習は8時間にわたる会談(ロブスター、ステーキ、アップルパイの夕食をしながらの意見交換も含めて)し、貿易面では中国によるサイバー攻撃、軍事面では‘太平洋に姿を現したツキジデスの罠’尖閣諸島をめぐる日中の対立、南シナ海におけるベトナム、フィリッピンと中国の領有権をめぐる対立が主な議題になった。
前者は中国のアメリカ企業へのサイバー攻撃による知的財産権の盗用問題である。その被害額は推定3000億ドル(30兆円)だから、オバマとしても看過できない。中国人民解放軍の上海を拠点とするサイバー部隊63198が、多くの米企業と政府のサイトへ侵入してデータを盗んだことを米側は特定している。
二日目の会議の席でオバマは、被害にあった米企業の例をひいて説明したが、中国側はそれを認めなかった。米中は共同でサイバー・セキュアリティ問題に取り組むことに合意したが、中国の出方によっては米中関係がこじれる可能性がある。
領有権に関しては「習は一歩も譲らず」「サイバー攻撃と領有権が議題になると‘ナショナリズムの閃光’を感じた」とニューヨークタイムズ紙が、首脳会談に出席した米高官を引用している。ということは、尖閣問題について米中の主張は平行線だったということになる。
しかし、良いニュースもある。両国が軍事交流を深める、北朝鮮の核武装阻止で合意、温室効果ガスHFCの製造・使用の削減合意がそれだ。CO2排出量で世界1位の中国と世界2位の米国のHFCについての合意は、大量の削減になるので地球温暖化阻止への効果は大きい。
 |
| 異例の米中首脳会談 AP |
オバマは初めからこの会談を、ツキジデスの罠を回避するための第一歩と位置付けていたのではなかろうか。オバマは胡錦濤とは12回も会談したが、いつもメモを読むだけの彼に失望していたという。時にメモなしで率直に語ることが出来る習との会談が実現したことの意義は大きい。
中国は米国のアジア回帰を自国の封じ込め政策だと疑い、米国は中国の領有権主張を危険な拡張政策だと不信の眼で見ている現時点で、両首脳が時間をかけて意見を交わしたのは胡時代には考えられないことだ。
習が記者会見で新しいタイプの大国関係を提唱し「中米は過去の大国間の対決と紛争の悪循環から脱け出て、新しい道を見つけるべきだ」と語ったのは、ツキジデスの罠を意識しての発言だろう。
英語でagree to disagree(直訳すると‘見解の相違に同意する’、砕けて言うと‘あなたの意見に賛成はできないが、あなたがそう考えるのは理解できる’)という外交用語があるが、これは‘まずはお互い厳しい現実を認めて、じっくりやりましょう’とも解釈できる言葉だ。米中首脳の間でこれが暗黙の了解になっているのではないだろうか。
習の記者会見での発言はこれを裏付けているように思える。「オバマ大統領とわたしは、これから手紙、電話、会談、相互訪問をつうじて緊密に連絡を取り合う。適切な時期に、北京で今回と同じような会談をもちたいので、大統領を招待した」
この首脳会談を内外のメディア、識者が論評しているが、わたしはハーバード大学の政治学者ジョセフ・ナイ教授の評価「今回の米国大統領と中国首脳の会談は、40年前のニクソンと毛沢東の会談以来、最も重要なものだった」(ニューヨークタイムズ)に一番注目した。
ナイは、ソフトパワーの概念の提唱者、日米同盟の重要性を説く学者として知られ、国家情報会議議長や国防次官補を歴任したベテランだからこの言葉は重みがある。彼がここまで会談の歴史的意義を語るからには、相当の裏付けがあるのだろう。
オバマは当初からこの会談を通じて、習との個人的関係を深めるきっかけをつくり、深刻な争点については次回からと考えていたようだ。
土曜日の朝、オバマと習は通訳だけを連れて二人で散歩しながら、50分歓談している。その間、彼らはなにを話したかは漏れてこない。
いや、ひとつだけ漏れてきた話がある。オバマが‘習に運動していますか’と尋ねると、中国人通訳が1000メートルを誤訳して‘毎日1万メートル泳いでいます’と習が答えたので、オバマが唖然としたという。ともあれ、側近をも外したこの50分間、二人は波長が合ったのだろうか。
今回の首脳会談が米中関係の大転換点になるだろう、というナイの評価の成否については、しばらく時間がかかりそうだ。が、米中間でひとつだけ確かなことがある。それはツキジデスの罠の危険性だ。ハーバード大学のアリソンとナイの師匠であるヘンリー・キッシンジャーも「米中の軍事衝突を避ける努力をするのが両国のリーダーの義務である」(BBC)と言っている。
今回の米中首脳会談は、尖閣問題で中国と対立する日本にとって極めて重要なものだった。米中が建設的関係への道を探ろうとしていることは歓迎すべきことだ。米中接近などと猜疑心で見ないほうがよい。
それにしても、日中関係は行き詰まったままである。李克強首相は「尖閣諸島は日本が盗み取った」とどぎつい非外交的言葉で領土権を主張する。片や菅官房長官は、戚建国副総参謀長の‘尖閣棚上げ’発言のシグナルを「棚上げすべき問題は存在しない」と取りつく島もない応答をする。
両国が建前を主張するだけでは、対立が先鋭化し不信が高まるだけだ。安倍もオバマも習も対話での解決を訴えているわけだから、日本は知恵をしぼって突破口を開く創造的外交ができないものだろうか。
米中和解、米ソ核軍縮、ベトナム和平交渉などに取り組み、20世紀外交史にその名を刻んだキッシンジャーは、創造的あいまい外交の美徳を説いている。尖閣棚上げでよいではないか。あの小さな無人島をめぐって戦争をするのは愚かなことだ。
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール
土野繁樹(ひじの・しげき)
フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て
「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |