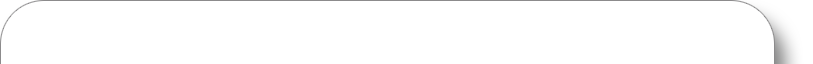髙木 亨
避暑地軽井沢
 写真1 賑わう軽井沢駅南口とアウトレットモール
写真1 賑わう軽井沢駅南口とアウトレットモール 4月は諸々の出来事があり、お休みを頂いた。今月からまたぽちぽちと書き進めていきたい。ゴールデンウィーク、久しぶりに軽井沢の自宅へ戻ってきた。「軽井沢の自宅」というと、セレブリティあふれるような感じだが、そんな上品なものではない。約10年前に、当時軽井沢勤めだったカミさんと結婚する際に、やってきてそのまま。その後、行きつけの喫茶店マスターの家を譲ってもらった。そんな話である。
「軽井沢に自宅がある」というと、(腹の底でどう思っているかわからないが(笑))ほぼ100%の人が「うらやましい」とか「いいですねぇ」という。また、地域おこしの仕事をしていると、とくに農村部・高原などで「軽井沢みたいに…」という言葉に出くわす。この前も、福島県のとある高原にある温泉の活性化をしている方から、「軽井沢みたいに観光客を呼んで…」ということも聞いた。これら軽井沢へ対するイメージとはどこから来るものであろうか。
軽井沢町は年間760万人(2011年度)が観光に訪れる「観光地」である。そのうちの400万人が6月~8月の夏季に訪れている。夏季に集中した「避暑を目的とした観光地」といえる。しかし、「観光地」が軽井沢町の特徴かというと、そうではない。軽井沢町には「別荘」が約1万5千戸ある。軽井沢周辺の市町村をあわせると、この地域に相当数の「別荘」が存在している。「軽井沢」の地域イメージの本質はこの保養を中心とする避暑と別荘および別荘地文化にあるといえる。
軽井沢町の歴史を紐解くと、「避暑地」としての始まりは、カナダ生まれの英国聖公会宣教師であったアレクサンダー・クロフト・ショー(A・C・ショー)氏と友人のジェームズ・メイン・ディクソン氏(東京帝国大学教授)が1885年(明治18年)に軽井沢を訪れたことにあるといえる。その後も両氏は家族を連れて毎年訪れている。そして、1888年(明治21年)にA・C・ショー氏・ディクソン氏ともに別荘を建てた。これが軽井沢初の別荘である。夏の気候が気に入ったほか、宿場としては寂れており、遊女や酒場がなかったことも軽井沢の地を気に入った理由とされている。
A・C・ショー氏らは、日本に来ていた友人らを呼んで夏の軽井沢の良さを伝え、多くの外国人たちが軽井沢に別荘をもとめ、一夏を過ごすようになっていった。また、外国人を受け入れ、彼ら向けのサービスを提供するホテル(現在の万平ホテル)や、食料を提供する店舗などを作り上げていった地元住民たちの存在。キリスト教の教えに従った「保養地」としてのイメージはこの頃作り上げられていったといえる。大正期に入ると、日本の文化人たちがこぞって軽井沢へ来るようになり、堀辰雄に代表される「軽井沢文学」が生まれていった。
 写真2 静かな別荘地
写真2 静かな別荘地 さて、軽井沢に関係する人々は、こうしたイメージを保とうと努力してきた。古くは外国人滞在者たちが中心となってつくった「避暑人会(1896年、その後軽井沢避暑団、のちの軽井沢会の前身)」をはじめ、文化的な発信をする「軽井沢通俗夏季大学(1918年、現、軽井沢夏期大学)」などの活動、戦後、1951年には軽井沢町売春取り締まり条例、軽井沢国際親善文化観光都市建設法公布等々、軽井沢の環境を守る取組がなされている。最近ではリゾートマンションの乱開発を防止するための「マンション軽井沢メソッド宣言(2005年)」が発表され、軽井沢町内における大規模マンション開発が制限されている。
紆余曲折あるものの、現在に至るまで軽井沢町はじめ住民・別荘族が努力しながら「イメージ」を大事にし続けているところに、軽井沢の魅力があるといえる。一朝一夕に出来上がったものではないこと、そのイメージにあぐらをかいているわけではないことを強調したい(最近、あぐらをかいているのでは、という声も聞こえてくるが…)。
話を元に戻す。「軽井沢みたいに…」という前出の言葉。どうとらえるべきなのか、常々考える。「軽井沢みたい」だからといって、首都圏など都市部から観光客が来るか、答えは当然NOである。あたりまえであるが、地域の魅力がなければ観光客はやってこない。また、本当の軽井沢を知っている層はおそらく相手にもしないだろう。軽井沢と同じ事をやってもそれは物まねにしか過ぎないし、同じ事はできない。どうすれば良いのか、「歴史の積み重ねを大事にして、地域の持つ本質(地理学の言葉で言う「地域性」)をいかにとらえて、育てていくのか、それしかないのでは、そして新たな価値観を創造していくこと」ではないかと、本稿を書きながら考えた。
笑い話がある。軽井沢駅を降り立った観光客が駅の係員にこう尋ねた。「さて、私たちはどこを見たらよいのでしょうか?」。つまり、軽井沢町は、大きな温泉地や、目玉となる名所・旧跡があるという「観光地」ではない。「ここを見れば軽井沢に来た」という場所はない。そうした「目玉」がない代わりに、浅間山麓の自然景観、先人たちが築きあげてきた「避暑地」としての「イメージ」があり、それを守ってきた人たちの存在、そして、軽井沢の持つイメージへの「あこがれ」がある。軽井沢町にある多くの「観光」施設はその流れの中に存在しているだけである。この文脈無しに、軽井沢町の観光は成り立たないし、そこから外れたものは長続きしない。
 写真3 夏の浅間山
写真3 夏の浅間山 このような文脈をいかにつくりあげていけるのか、また、ターゲットの客層に対してどのように発信していくのか、フクシマを含めた「観光客を誘致したい地域」の課題である。
<参考文献>
小林収(1999):『避暑地 軽井沢』櫟.284p.
軽井沢文化協会創立50周年記念誌編集委員会編(2003):『軽井沢120年―軽井沢文化協会創立50周年―』櫟.186p.
【フクシマ・センダイ・カルイザワ それぞれの地で考えること バックナンバー】
著者プロフィール
髙木 亨(たかぎ・あきら)
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任准教授
博士(地理学)、専門地域調査士。
東京生まれ、東京近郊で育つ。
立正大学で地理学を学ぶ。
立正大学、財団法人地域開発研究所を経て2012年3月から現職 |