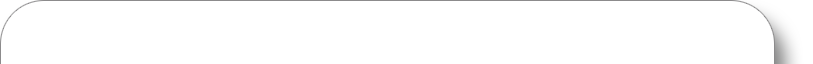土野繁樹
わが家の東側の春景色
やっと長かった冬が終わって、サン・ジャン・ドコール村に待ちに待った春がやって来た。当地で暮らしはじめて一番寒く、毎日のように雨が降る異常な冬が去り、無風、気温20度の正真正銘の春日の今日は心が弾む。納屋から取り出した黄色いデッキチェアーに座って、コーヒーを飲む。夏雲のような逞しい雲を眺めながら、健康回復のありがたさを思う。(2月の中旬から2週間、ヴィールスにやられ左頭部の頭痛と左眼が腫れてミニお岩になり医者にかかった)。
ポカポカ陽気に誘われて散歩にでかける。玄関をでると、坂を上がってきたルノー車が停まった。わが家からすこし離れた丘の上の一軒家で暮らすカレー夫人エレンだった。「ヤードの調子はどうですか?」と彼女が聞く。「おかげさまで、咳も止まったのでもう大丈夫でしょう。血液検査の結果、なんの問題もなく安心しました」と答える。
一昨日、エレンはわが奥方が悪性のインフルエンザにかかり10日間も寝こんでいるのを聞きつけ、見舞いに来てくれた。医者に往診してもらったが、なかなか治らないので、風邪ではなく他に原因があるかも知れないので、血液検査をしたいと言うと「それじゃ、わたしが知っている看護婦のマゾーさんに来てもらいましょう」と言い彼女は一端自宅に帰った。しばらくして「病人にはなによりスープよ」と言いながら、大きな瓶に入った作ったばかりの二種類の野菜スープを持ってきてくれた。翌朝、マゾーさんが来て採血し、町の血液分析所で検査した結果は問題なしだった。隣のバトラン夫人も医者の往診の手配をしてくれた。隣人の親切が身に沁みる。
池のガチョウ
わが家に隣接して5000坪の大きな池がある。パリの住人の別荘の敷地内にあるのだが、家主はふつう不在なので、たまに池を1周する。エレンにお礼を言ったあと、池の周りを散歩していると、ガチョウのつがいが目の前をゆっくり歩いていた。やがて彼らは、池に入り一直線に進んでいった。夫唱婦随か婦唱夫随なのかは分からない。
村につながる道の右側は野原で蛇行するコール川が見え隠れし、右側は小高い岩崖になっている。崖のくぼみを見るたびに、ここはクロマニヨン人の住居だったのでないかと思う。村の入り口まで1キロの道沿いに4軒の家が点在している。わが家の別棟の洗面所や台所を新装してくれた建築業のカスターニュさんの家、昨年引っ越してきて友人になったイタリア人夫妻の水車がある家、5年前に農家の廃屋を自力で改築し見栄えのする住居にしたオランダ人夫妻の家、川沿いの庭があるモロッコ人夫妻ラヒトさんの家がある。わが家のすぐ隣はバトランさんとドモントさんの家だから、これをいれると7軒中(わが家を含めて)4軒が外国人の住居ということになる。
人口350人のサン・ジャン・ドコール村には、外国人が所有する家(半分は別荘)が24軒もある。国籍はモロッコ、英国、アイルランド、オランダ、ベルギー、リトアニア、カナダ、イタリア、ドイツ、アメリカ、スウェーデン、日本と12ヶ国にもなる。ドルドーニュ県の小さな村がなぜこんな国際村になっているのか。その背景には、EU市民であればEU圏のどこにでも暮らせる、というEUのシェンゲン協定の存在がある。EU圏内ではヒト、モノ、カネの流れが自由になり、国境が消滅している。その結果、グローバル・ヴィレッジが出現したわけだ。
村の外国人のなかで一番多いのは英国人で、その次がオランダ人で、その他の国はそれぞれ一人か二人だ。抜群の環境、不動産の安さ、肉や野菜の旨さに魅せられて、ドルドーニュ県で暮らす英国人は多い。昨年末、村の親友(夫のロンはカナダ人、妻のオナはリトアニア人)のお宅でパーティがあったが、客はフランス人と外国人が半々で、英国人が7,8人はいた。隣に座ったアイルランド人の知人がワイングラス片手に「何百年もかけて、アイルランドから英国人を追っ払ったと思ったら、なんたることか。この村は英国人でいっぱいだよ」と言っていた。こんなのをアイリシュ・ユーモアと言うのだろう。
教会の鐘塔(左)と城の尖塔(右)
1キロ歩いて村の入り口に着くと、11世紀に建った教会の3時を告げる鐘が鳴った。村の広場では、城を背にして陽光を浴びながら4.5人の村人がペタンク(伝統球技)に興じている。中世にできたコール川にかかる風情のある石畳みの橋を渡ると、リトアニア人のオナが、アメリカ人のメリーと語らっていた。建築技師のオナは夫の人類学者ロンと5年前に、15世紀に建てられ20年も放置されていた家を買い、資材を購入しほとんど自力で大改造をし、趣味のいい快適な生活空間を作り上げている。
米国ケンタッキー州出身のインテリア・デザイナのメリーは、夫のジムと当地で暮らすこと20年のベテランだ。彼らは村の中と、村の外れの丘の上の廃墟を再生した家を持っているが、内装はまるで建築雑誌 ’Architectural Digest’に出てくるような輝きがある。二組の外国人夫妻(オランダ人夫妻も)は、村の退役将軍フォルニエさんが言うように、誰も手をつけなかった廃屋を蘇らせ村を美しくした功労者だ。奥方とわたしはこの二組の夫婦とは波長が合い、世界観と人生感が重なるところが多く最も親しい。
久しぶりに会ったメリーが「もう頭痛は無くなった?」と聞く。「ぼくはすっかり良くなったが、ヤードがインフルエンザで10日も寝込んで、やっと元気になりつつあるよ」とわたし。「イタリアへは行ったの?」と彼女が尋ねるので「いやーそれがドゴール空港まで行ったのに、雪のためフライトがキャンセルになるは、大混乱の空港でヤードの体調が悪くなり医療センターで診察を受けるやで、結局、翌日こちらへ戻ってきたよ」と言うと「楽しみにしていたのに、それは大変だったわね」とえらく同情してくれる。「まあ、航空券やホテルの代金はムダになったけど、飛行機が墜落して死ぬよりいいよ」とわたしが言うと、彼女は「それはそうね」とあいづちを打ってくれた。
家に戻る道すがら、ひさしぶりに医者の世話になったせいか、10年前のわが病院体験を想いだしていた。その日、わたしは新品自転車のハンドル操作を間違え横転、鎖骨を折ってペリギュー県立病院に入院したのだが、翌日の昼時に看護婦が「赤にしますか、白にしますか」と聞いたのにはビックリした。フランスの病院では患者にワインをだすのである。その頃はまだフランスの医療保険制度に入っていなかったので、一泊入院は高くついた。しかし、あれは5万円の超高級ボルドー・ワイン一杯の値段だったのだ、と自分に言い聞かせている。
フランスの国民皆保険制度は、日本の国民健康保険のように、資格取得のための支払い義務がないので助かる。フランス市民あるいはEU市民(フランスと相互取り決めのある国の市民)には、自動的に日本の国民健康保険証に当たるVitaleが発行されるが、これには費用がかからない。
今回のわたしの場合、町の総合医のところで診断をしてもらい、彼の署名入りの薬のリストをもって薬局に行き、それで治療したのだが、総費用は約200ユーロ:2万5千円だった(診察費23ユーロを2回、レントゲン50ユーロ、薬100ユーロ)。薬代の明細を見ると、政府が50%負担していた。この部分は消費税20%などの税収でカバーしているということになる。Vitaleが適用される範囲が限定されているので、多くの人々が自己負担で民間会社の医療保険に加入している。
それにしても、フランスは薬の国だと思う。わたしが利用した鎮痛剤など3種の薬は少ないほうで、奥方は2回の医者の処方で7種類もあった。人口3000人の隣町ティヴィエには3つの薬局があり、それぞれの店に薬剤師が4,5人いて、訪れる人が絶えない。薬嫌いの奥方に言わせると、フランスの医療サービスはスウェーデンと同等の高レベルだが、薬に依存しすぎということになる。調べてみると、フランス人の薬消費量はヨーロッパ一だった。
かりんの花
春の空気をいっぱい吸って家に戻ってきて、タンポポの花で溢れる庭を一巡する。タロウドリの鳴き声が聞こえてくる。水仙の花が咲き、柳に葉が付きはじめ、かりんの花(写真)が満開だ。かりんは東京にいる2歳の初孫の名前でもあるので、この花にはとりわけ愛着がある。
奥方がインフルエンザでダウンしている間、スーパーでの買い物と料理は、わたしが担当した。リスト片手にスーパーで食料や日用品を買うのは慣れているが、料理は辻クッキング・スクール卒で料理教師の母をもつ奥方が仕切ってきたので一苦労だった。それでも、彼女の指示に従って作ったポーク・フィレ、ハンバーグ、アンリーブのグラタンは合格点をもらった。蕎麦つゆやマドレーヌ菓子の作り方をマスターしたのも収穫だった。食べる人、皿洗う人から、料理する人への進化である。
今晩は、やっと元気になった奥方が台所に立ち、料理長として腕を振るった。わたしは傍で、彼女の作る肉野菜スープの料理法を質問しながらメモをとり後日に備えた。さすが、師匠の料理は旨い。食事のあと、書斎の窓を開けるとフル・ムーンだった。
満月が 池に映りて 春来る
【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】